「日常ー学び」では発達障害を持つ子の子育てあるあるや、我が家の場合の発達エピソードについて、日ごろの子どもたちの行動や発言、そこから学ぶこと~ちょっとクスっと笑える日常の会話まで、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
”切り替えが苦手”と日常生活への不満、不安の関係
今回は発達障害の特徴の一つである切り替えが苦手について、次女の場合の現れ方、私の今のところの対応方法と思うことを書こうと思います。
インフルエンザの予防接種のお話の時に少し書いたのですが、切り替えが苦手な特性がどういったことに現れるのか、そこにどう向き合うことが必要だと思っているか、私の感じていることをより詳しく書こうと思います。
あくまで私が次女を見るうえで感じてきたことと対応方法なので、子育てする母親の一意見としてとらえていただけると嬉しいです。
参考:発達障害の気持ちや活動の切り替えをコントロールできるようになるには
社会生活のために”切り替えが苦手”への対策が必要
発達障害の特徴の一つに”切り替えが苦手”というものがあります。
これは小学生くらいになると徐々に本人の中でも違和感や周囲に対しての困り感が出てくる要因の一つになってくるかと思います。
私個人の感想としては、次女を見ていると、そのままでいると社会生活の中でどんどん不自由になっていってしまうだろうなと思います。
社会生活していくには、できるなら自分の特性と向き合って、コントロールすることがある程度求められるだろうことは想像に難くありません。
そのためには、コントロールをするための練習をしてみることが大切だなと日々感じているところです。
そのために療育があるわけですが…
私は、この療育の存在を知った時、子どもに向き合うには親も同じ専門知識をしっかりと身に着けないといけないのか、とか、それ通りに一通りやってみてから子どもの向き不向きに合わせて取り組んでいけないと駄目な親なのではないか?という思いに駆られました。
そうして、いざ、見聞きする方法を取り入れてみると、いまいちしっくりこず…。
と、言いますか、ほとんどが素通り状態で効果を感じられない。ということが起こりました。
私のやり方が正確ではなかったり、中途半端だったのかもしれませんが、こういった練習方法がうまく子どもたちに響かない日々の奮闘の中で、何となく矛盾を抱えるようになりました。
それは、参考書通りの対応に固執すると、”子どものできないがより意識されてしまうこと”や、”頭が固くなって子どもの状態をしっかり見る、感じることができなくなってくるということでした。
そんな中、支援事業の方に相談したところ、家庭で療育と同じことをしても、子どもにとってリラックスできる場所ではなくなったり、負担になることもあるかもしれないと寄り添っていただき、「ああ、そうか、専門家はそのためにいるのだから、それはそちらに任せよう。」と思い直して少し安心したということがありました。
そして、我が家は我が家で、親だから、身近な存在だからこそ、より子どもの心の近くに寄り添ってできることがあるはずだと思いました。
専門のことは専門家に頼り、私は私のできる子どもへの理解を深めようと行動し、感じ、考えること。結局それが一番!!と思いました。
つらつらと書いていますが、要は、私は通常の子育てと同じで、子どもたちを見るということに徹すればいいんだよね。と思ったということです。
というわけで、私なりの対応がどうなっているのかと言いますと、次のようになるかと思います。
ASD 自閉スペクトラム症を持つ次女への切り替えのための対応
〇 次女への心構え
切り替えへのスムーズなサポート
安心貯金をしておく
〇 見守る家族の心構え
できないときに落ち込まない
一つずつまとめてみたので順番に書いていきます。
次女への心構え
- 切り替えの思考をできるだけスムーズにサポートすること
- 切り替えの仕方を本人の意思で納得して選択できるように提示してみる
- ひとまず落ち着く時間をつくる
- 安心貯金をしておく
- 本人が受け入れられる余地を残していること
1.切り替えの思考をできるだけスムーズにサポートする
1にはさらに2つあります。
①つ目は”切り替えの仕方をできるだけ本人の意思で納得して選択できるように提示してみる”ということです。
次女の場合、「不満だけどとりあえずここは収めておこう」とか、「怒られて我慢せざるを得ない」ということになると、それが確実に蓄積されてしまうように感じます。
そして、その蓄積が次に不満や不安に思った出来事で改めて再燃して、怒りのパワーにエンジンをかけてしまうように感じます。
また、この不安や不満が大きい、もしくは小さくてもいくつもたまってくると、ふと思い出していきなり怒りだしてしまうこともあります。
そしてこの不安、不満の積み重なりが日常の生活スピードに大きく影響しているようもにも思います。

というわけで、我が家の日常の具体例を挙げてみます。
例えば宿題で音読をしようとしていたとします。
ご機嫌で音読のページを探していますが、なかなか見つかりません。
だんだん嫌になってきた次女は愚図りだしてしまいます。こうなると30分~数時間何事も進まなくなります。
そこで私は、しばらく愚図りを傍観してから状況を聞きます。できれば本人の口から説明してもらうことも大事だと思っています。(自分の気持ちの確認)
一緒にそのページを探そうか?と言って、すんなりと受け入れてくれればいいのですが、「一度やって見つからなかったから」と嫌がる時が結構あります。
そういう時は本人がどうしたいのか?を聞きます。どうしたいのかという抽象的な質問だとうまく答えられないことが多いので、この時選択肢を挙げます。
例えば、まず宿題をしたいのか、したくないのか
本人がそれに取り組む気があるのか、取り組むことが嫌なのかを聞きます。
しないと答えるのならしなくてもいいよと伝えます。といいながら、時間を空けて機嫌のいいときに「あ!そういえば、音読してみる?」などと声をかけてみたりもします。 笑
できなかったときは、学校に伝えられるように子どもの状態を伝えておくとスムーズだと思います。こういう時、学校の理解を得ておくと親の気持ち的には楽かなと思います。
「する」と答えれば、「じゃあどうぞー~。お母さん聞くから」などとあくまで普段通りに接します。(我が家の場合、ここで「おお~!すごーい!!」などと拒否していたことを再確認してしまうようなリアクションをするとまた否定的になって失敗することが多いからです。笑)
ここですんなりと音読してくれればラッキーです。
まだなかなかやり始めない場合は、音読を勧め過ぎずに何となく会話をするなどして、あえて一度違うことに気をそらしたりします。
そろそろ切り替えられるかな?と様子を見ながら、「音読する~?」と、時折はさみながら 笑
何となく雑談などをします。
子どもが落ち着いてくるとその場を離れて家事などをしながら雑談をして、できないに固執する気持ちと時間が過ぎるのを待ちます。
嫌な気持ちが小さくなってきたかな?と思う頃に最後の一押し。「さぁて、音読するか~?」
取り組んでくれればラッキーです。
本人が宿題が済んでいないことにこだわらない状態なら、一度、宿題の前に時間を決めて遊ぶなど全く違うことをはさんで仕切り直したりもします。
本人が怒ることをどうしても納められない状態のときは②”一度落ち着く時間を作る”です。私のしている方法としては単純です。
先述もいかに落ち着いてもらって話が入るようにするかということでしたが、ここではもう少し直接的な方法です。
例えば次女が猛烈に怒って地団駄を踏んでいるとします。
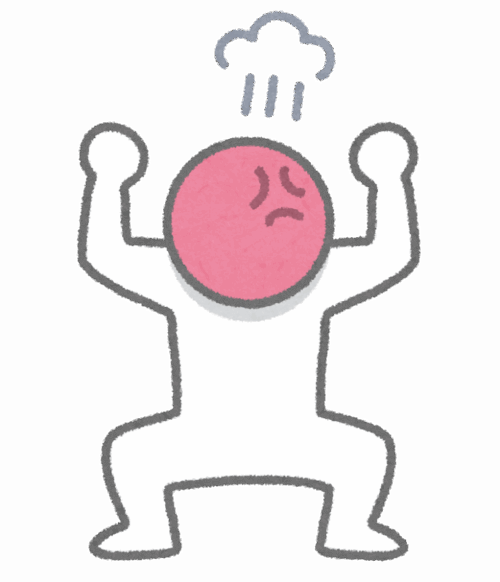
まず、しばらく地団駄を傍観する勇気がいります。(怒りのエネルギーをすぐに封じ込めない方がいいと個人的には思うからです。)
それから様子を見て、手を広げて「おいで」と呼びかけます。そして来てくれたらぎゅっと抱きしめてあげます。
そこで落ち着いて収まることはわりとあるように思います。
これはテンションが上がりすぎているときにも使ったりします。
ここで私が少し気を付けていることがあるのですが、それは、あくまで本人の意思で私のところに来てもらうことです。
こちらに物理的に歩み寄ってくる間に落ち着いてきたり、言ったことについて少し受け入れてみようと思ってくれたりするように思います。
それから単純に私から行くと、そういう心境じゃないまま無理やり感があるようで、余計に怒らせてしまうことがあるからです。
2.次女が受け入れられる余地を残していること
そして1が成り立つ環境として大切だと思うことが、安心貯金です。
と言っても当然、実際にお金を貯金することではなく、これは私が勝手に名付けた呼び名で、”日々に安心感を増やすこと”です。これが次女が話を受け入れられる余地を残すことになると考えています。
ASD傾向のある人は感覚過敏や脳の働きなど、様々な要因で日常生活において不安が強いようです。我が家の ASD傾向の見られる ちち も、特性が出る背景には不安がとても大きいのだろうなと思うところが多々あります。
不安を感じやすいだろう次女の脳に、安心を与えてあげられる環境をどれだけ整えてあげられるか。つまり、毎日の細かなストレスを減らしてあげるこことが大切ではないかと思います。
私が次女に対して最も意識が必要なのではないかと考えていることの一つです。
特に、子どもはまだ経験不足でその不安がなにかを理解し辛く、何かわからない不快な気持ちを抱えているのだと見ていて感じますし、それによって怒ってしまったり、パニックになってしまったりしているように思います。
次女の様子から、その思考の特性に意識して接してくれる人が増えてくるたびに、日常の安定感が増えていくのを感じています。つまり、ストレスへの配慮があるとそれだけ不安になることを減らせるということです。
実際、私が次女の発達障害に気づいてからや、学校との情報共有、放課後デイサービスを利用し始めて、と、そのいい影響を日々感じています。
この、いわば安心貯金が、いざという時の怒りの発動をコントロールできる心の余裕につながるのではないかと私は思っています。
具体的には、初めから否定しない、本人の考えを聞き出す、わからないのであればわからないでもいいと伝える。どうしたらよかったのか一緒に考える。などですが、これは普通の子育てでも同様のことかと思います。ただ、少し、言い回しや伝え方に工夫が必要だったり、自分の気持ちに気づけていない場合もあるのでそのことを考慮したりすることが必要なのかな?と思います。
次女の場合は納得すると拍子抜けするくらいすんなり受け入れてくれたりするので、状況を本人のわかりやすい言葉で伝えたり、意向を聞いたりと寄り添うことが安心につながって、向き合おうとしてくれるきっかけになるように感じます。
と言っても確実に効果を発揮してくれるものでもなく、本人のとらえ方によって効果が出ないこともありますが、ある程度安心貯金がたまっているか、そうでないかでは、否定的なとらえ方やその事態の大きさを軽減できるように感じています。
それでいうと、当然、こっちが先に嫌になって怒ってしまうとこじらせる道しかないので、対応するこちらとしては忍耐修行になります。(もちろん、わかっていても怒ってしまうことも少なくありませんが…。)

そういう私は余裕のある時しかうまく対応できません!笑
見守る家族の心構え
そして見守る側にも必要だと思う心構えがあります。
それは、怒ってしまったり付き合いきれなかったときは、それはそれで今回はできなかったけど仕方ない!と捉えることです。
これは前向きな仕方ない!です。
できなかったことを悔いたままにするのではなく、次はきちんと聞いてあげようと前向きな原動力にすることが大切ではないかと私は思っています。
それから、こじらせてしまったなとか、怒ってしまったなという時は、自分に余裕がないのかも?と自分と向き合うきっかけにしてあげたいと思うようにするといいのかなと思います。
まとめ
親は誰でも子どもの専門家じゃないかな?と思います。
その子のことを見て、細かいけどその子に合ったちょっとした工夫を対応の中に見つけて、安心貯金を増やしながら、切り替える成功体験を増やしていければいいなと思うと同時に、親もありのままの自分と向き合うことで、できない自分も受け入れてともに成長していける関係に近づければいいなと思います。





コメント