「日常ー学び」では発達障害を持つ我が家の姉妹のエピソードや、そこから学ぶことと、ちょっとクスっと笑える日常の会話など、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
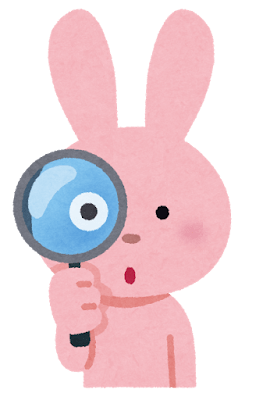
持っていたものをなくした幼い頃の次女
次女 「ない!」
はは 「探してみ?」
ぼーっと立ち尽くして一点を見つめる小人。(まだ幼少期の次女)
その視線の5センチくらい横にずれたところに目的のものがあります。
ぼぉぉぉぉぉぉぉーーーーー。
「ない!!」

!?!?!?!?!?!?!?
最初は衝撃的過ぎて、むしろ私に見えているものが幻かと疑ったくらいです。
パラレルワールドさながら、いやむしろ本当にパラレルワールドが存在しているのではないかという体験ができるほどの視覚的情報整理の苦手さ?。
今回は、発達障害の特性を持つ次女はそれくらい探し物が苦手という話をします。
1宿題につき2、3鉛筆見失う
その1 宿題のワンシーン
さて、こちらは三年生になった次女。なんやかんやあって、ようやく宿題を開きました。

ママ~?あのね、〇〇がね、△△でね、◇◇したらね~……。
あれ?鉛筆がなくなった。

え?!筆箱から出してないんじゃない?

出したもん!

ここにあるやん。(机の上のドリルの下から発見。)

あー 笑 あったぁぁぁ~ 笑
少し宿題に取り組みかけると、今度は姉の雑談が展開します。
長女のマイワールド展開!!!


ブンブン!!
長女ワールドにしばらく振り回され中…。

ママ~?また鉛筆が無いんだけどぉ?!

知らんやん…。

下。落ちてるよ。


あぁ~ 笑
あったぁぁぁ~ 笑
また少しの間、宿題に戻る次女。

集中してきたかな?(はは)

ママ~!?これわからん~!!!

どれ?

こ~れっ!こ~れっ!!こ~れっ!!!怒
膝で奏でる地団駄音と「こ~れ!」怒 音頭 で、はは の到着を出迎える次女

問題読んで~?
こっちは何個~?

〇〇ー△△=◇□ (かきかき)

あ!間違えた!………。? 消しゴムがないんだけど!?

○〇(次女の名前)、足元。
消しゴムが落ちている方と反対だけを見る次女。


ちがうちがう。反対。

ああぁ~!! 笑

ああぁ~!!じゃないよ~
何回見失いますか?(はは、心の声)
そうして、終ぞ、今手に持っていたものが出てこなくなることもしばしば。
とにかく置くたびに見失ってない?といった様子の次女なのでした。
(※ かく言う はは も、物を移動して一時的に見失うことは常習犯。特に携帯電話は一日に何回見失いますか?…。笑)
その2 ランドセルの用意
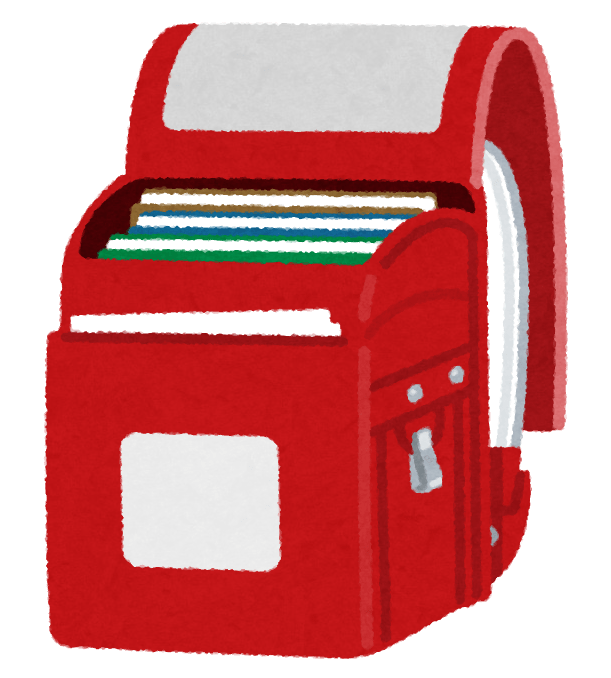
最近、用意が上手になってきた次女の場合
明日のランドセルの用意をしていた次女。
ランドセルに入れるものを時間割通りに集めていました。最後に宿題を見失った次女
次女「宿題が無いんだけどぉ!? 怒」
はは「〇〇(次女の名前)、ランドセルのふた、上げてみ?
次女「え??…どういうこと?」
母「ランドセルのふたを持ち上げてごらんって」
次女「え?どーうーいーうーこぉ~とぉ~!? 怒」
(※おそらく、ランドセルのふたは開けるか閉めるかしか聞いたことが無いので意味が伝わらなかったのだと思います。)
はは が、ふたを開けて寝かせてあるランドセルに近づき、ふた部分を持ち上げると、宿題たちが出現!!
次女「ああ~!あったぁ~!」
はは「いや、見えてたし。」
はは のツッコミに「あはぁ~」と笑う次女でした。
少し前までの次女の場合

明日の用意できたぁ~!
ご機嫌でランドセルを片づけに行く次女

やったぁ~!
次女の方を振り返るははが見たものは!?

えええええ!!!???
さっきまで宿題をしていたあたり一面に宿題や連絡帳、連絡袋が広がっているのでした。
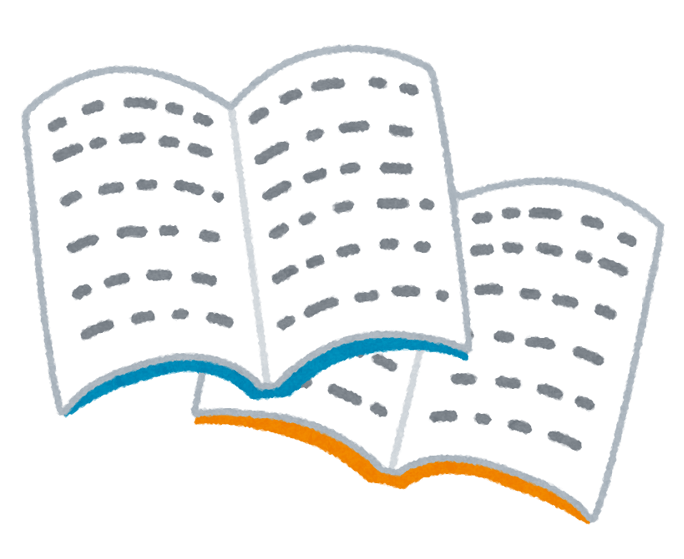
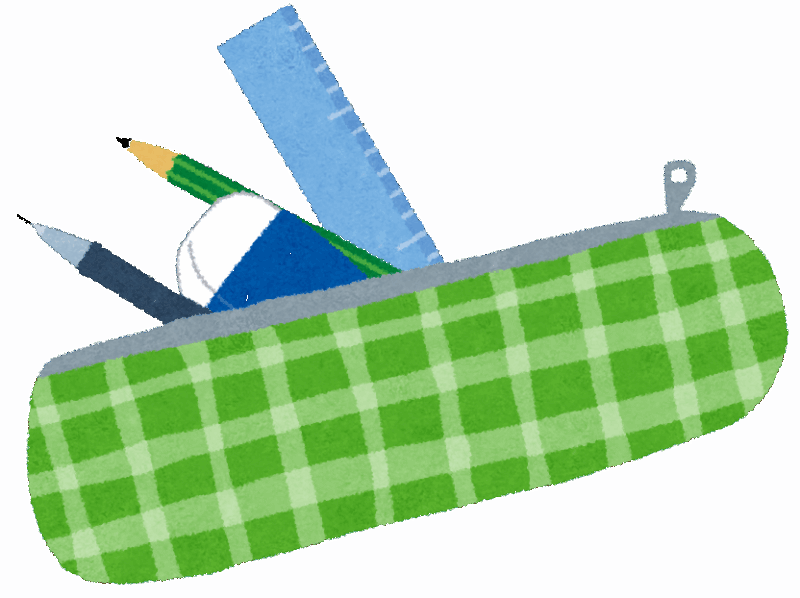

どういうことか?どうしたものか?と悩んでいた時期もありましたが、今はその時より少し成長もしているし、ま、いいか。
次女の探し物の原理
さて、こんな感じで、次女は、探し物が苦手です。
特に、今見えていないものは、無いものになってしまうようです。
しかも、
探さない
わたしから見ると、1秒も探したそぶりを見せず「なくなった!!」とよく怒っていました。
本人は探しているそうですが。
これも物の見え方、情報のとらえ方の問題なのだと発達障害の概念に出会って気づきました。
ここまで読んでくださった方は、そうそう!と思ってくださる方が多いのでしょうか?
さて、具体的にどういった側面からくる、どのような影響かと考えると、
おそらく、視野が狭かったり(その時のコンディションにもよると思われますが)、見えているものがすべて均等な情報として目に飛びこんできてしまい、それをうまく脳で処理することが難しいことで周囲の状態に気づきにくい、認識できていないということ、
そして予測が苦手なことから、「自分のそばに落ちているかもしれない」、「教科書やノートの下にあるかもしれない」、「無意識に筆箱にしまっているかもしれない」、などと考えることがまだまだ苦手だからなのかなと思います。
先述の会話は、現在小学3年生になった次女とのものですが、それでも幼稚園や1年生の頃と比べれば、比にならないくらい探し物をみつけることができるようになったと思っています。
ようやく経験の中で、物が消えたと思ったら周囲を見てみるということを学びはじめたということなのでしょう。
つまり、自分は鉛筆をよくなくして困ると認識できた結果、それを改善しようと、鉛筆が消えたら周囲を見る…
ことまでは学習、実践できるようになってきたのですが、まだあまり物をどかしたりしません。
ただ、できる時もあるので、予測のパターンを彼女の中で増やしていくことができれば、探し物の困りごとも減ってくると思います。
というわけで、次女の見失いレベルはまだまだ、見失いやすさ最高10の10段階評価として、8くらいでしょうか。どんどん困りを自覚して成長の可能性を広げていってほしいものです。
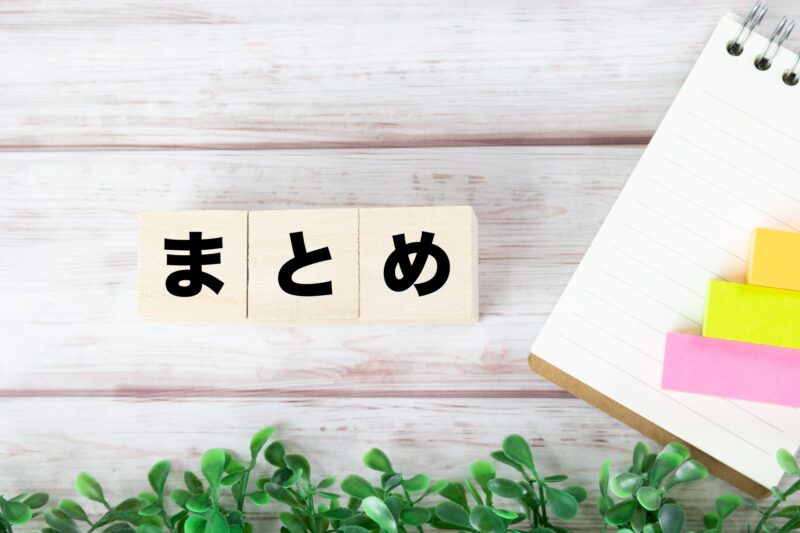
まとめ
ASDの診断を受けた次女は、すぐ目の前にあるものにも気づけないという、傍から見ると、まるでそれがパラレルワールドに存在しているかのような不思議な状態になります。
その経験をしたことのない人からすると、とても不思議な言動だと思います。しかもそれを繰り返しがちです。
今回の場合は探し方を学習するということが必要ですが、それを一度学習してもそこから安定してできるようになるわけではなく、本人の体調や心の安定度合や環境によってできるできないにはムラがあるように感じます。
それが発達障害傾向にある人たちの理解を、ますます難しくしていると思います。
ですが、見ている側が、それらが脳の働き方の特性によって十分考えられる出来事だと思ってみると、不思議な行動、理解できない行動から 「なるほど」と思える行動になるのではないかと考えています。
この記事で、物をなくす次女と私の会話を通して、その世界を少し体験してもらえればうれしいなと思います。
↓ 発達障害関係なく、誰しも自分を知るために読んでみるといいなと思った一冊です。とても分かりやすく事例と対策が書かれています。
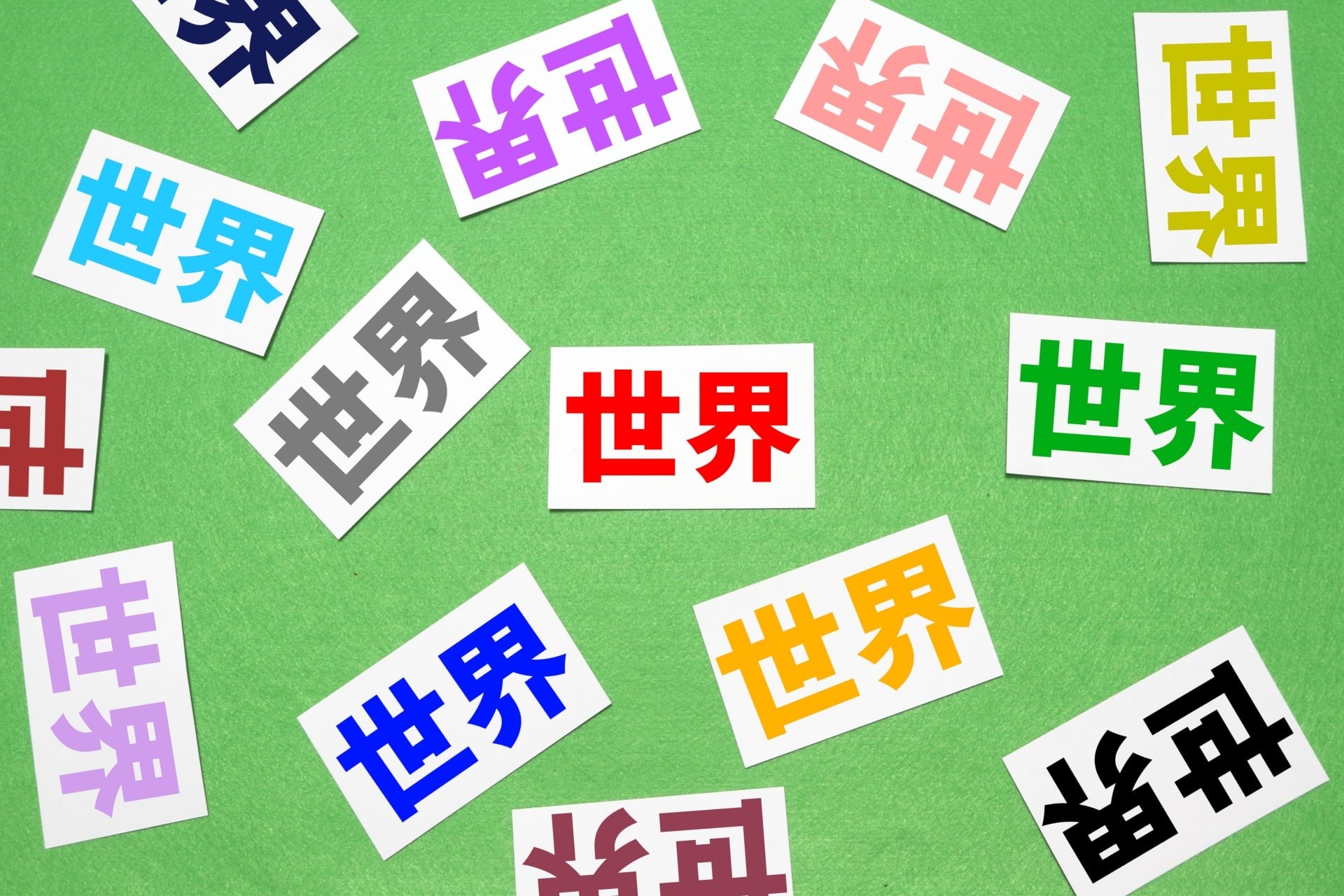




コメント