「日常ー学び」では発達障害を持つ我が家の姉妹のエピソードや、そこから学ぶこと、ちょっとクスっと笑える日常の会話まで、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
長女が5年生になって3か月ほどしたあたりでしょうか?
連絡帳を書いてきていないことが増えてきました。そして、どんどんと学校の宿題を終えられなくなっていきました。
今回は前回の『長女のイライラがぐるぐるする話』からさらに長女の負担が増えていく様子と、我が家の対応の話を書きます。
宿題が永遠にやる気にならない
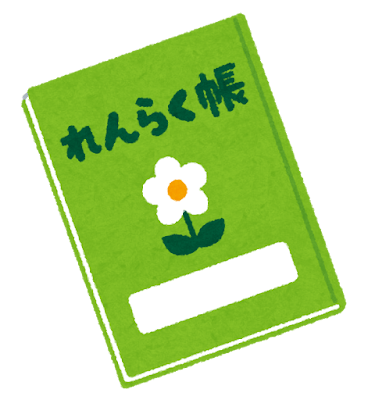
実は、次女の時に発達検査を受けようと思ったのも、連絡帳が書いてこられないことと、宿題が4時間ほどかかる日常がきっかけでした。正直同じ現象が起こると思っていなかったので驚きましたが、発達障害を持つ子の特性上、この2つは特性が出やすいことなのかもしれません。
まず、連絡帳をどのように書いているのかと担任の先生に確認しました。
すると、5年生になってからは、登校してから各自のタイミングで連絡帳を書くようになっていたようでした。
それを聞いたはは(私/はゆまーま)は、そのことに対しては対策が打てそうだと、担任の先生に一日のスケジュールの中で一番時間が取れそうな時間帯を指定して、連絡帳を書くタイミングを決めてやってくださいと伝えました。
そうすると、書き忘れる日が減りました。時折書いてきていない日はありますが、格段に減りました。
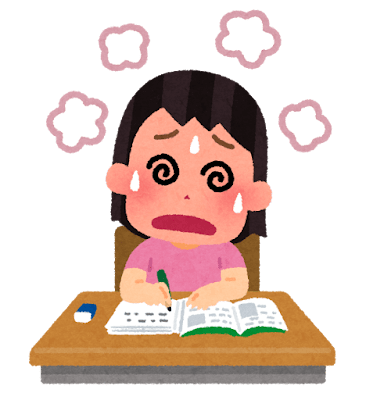
さて、問題は宿題です。
宿題に関しては、数日間の間で、1時間が1時間半になり、2時間、3時間、遂には週末の3日をかけてもなかなか終わらず、登校日の月曜日の朝にやっと終わらせられるという状態です。平日は終わらない日が当たり前になってきてしまっていました。
最近の長女の変化に気づき始めた頃は、「最近、疲れてるなぁ…。夏で暑いからかなぁ?」と思っていたはは ですが、こうなってくると状況も違ってきます。
状況を踏まえて長女を見ると、やはり特別疲れが強く、自分をコントロールできなくなっているように感じるのです。
どうにかきりかえられるようにと誘導はしますが、最後は本人の意志、そこが長女自身にもどうにもできない感覚を感じていました。
明らかなシャットダウン状態
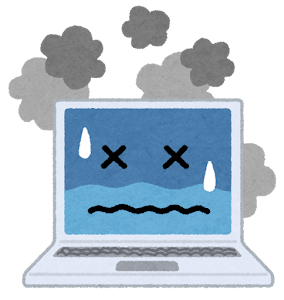
長女は赤ちゃんの頃から昼寝をほとんどすることのない子どもでした。夜もすんなり寝てくれなくて困ったものです。
そんな長女はそのま成長しました。基本的には風邪をひいても高熱を出しても日中寝ることのない子です。
ですが、5年生になって何となく休みの日やカゼをひいたときに寝ている姿を見ることが出てきて、気になるようになりました。(本来なら寝て当たり前なのですが 笑)
そのうちに連絡帳と宿題の問題が出てきたのです。
- 宿題が進まない
- 解き方がわかっていても進まない
- 普段は解いている計算問題もわからなくなる
- 普段よりも文章問題が入ってこなくなる
結果、宿題をやり始めるとフリーズして、少し宿題に手を付けられたか?と思えばまた眺めているだけの状態になります。
親が言っては逆効果、言うと長女が過剰反応して怒ってしまうことが、以前にも増して増えました。
けれど言わなければ永遠にやり始めようという態勢にもならない。
相当な時間をかけて、何とか宿題をやる体勢はとりますが、気づけば、長女は横になって寝てしまっているのです。あの、そうそう寝ることのない長女が!!
どう考えてもおかしいと思いました。その姿はまさにシャットダウンという言葉がぴったりでした。
そして、長女が昼間寝てしまうことにはとても意味があることを、はは は経験上知っています。

かなり限界を超えてきている。対策をとらないと!
長女への対応
発達検査
そこで、私が必要だと思った対策としては、次女と同じくになるのですが、家庭、学校、そのどちらでもないコミュニティー(つまり療育)の3つからのアプローチです。もう、この時点で療育も体験させてみるほうがいいと思いました。
そういった経緯で発達障害の検査をすることにしました。
私にとっては、診断が重要ではなく、私の目に映る長女のヘルプサインに対応ができればどちらでもよかったのですが、やはり、説明する際に基準となるものがある方が説得力も増します。
ところが、この時の心理検査(発達障害を)では微妙なラインだったようで、診断は下りませんでした。ただ、先生も気にはなったようで、追加の問診票を渡されました。
それから私は、個人的に学校へ長女の状況を伝えること、療育を受けられるように手配することを考えました。
学校への相談
時期は5年生の夏休み前、まず学校に相談をしました。
長女の担任の先生はとてもまじめな人といった印象でしたが、発達障害にはあまり詳しくなさそうで、このころには完全に宿題が終わらせられなくなっていたので、長女の状態を連絡帳で伝えてはいました。
が、いまいちニュアンスが伝わっていないようでした。
ただ、ひとまず対応はしてくださり、後日私とスクールカウンセラーさんとの話の場を設けていただきました。
そうして学校としての対応が形づいては来ましたが、その間もみるみるうちに長女は悪循環に陥っているようでした。
そんな長女の姿に、担任の先生にもある程度具体的に現状の把握をしていただかないと厳しいと判断して、懇談の際に追加で
長女の状態のさらに具体的な説明、
それが、私が現状一番当てはまっていると(ヒントになると)とらえている発達障害の要素からくるのではないかと考えていること。
そして、当時、はは としては、これは長女の説明だ!と思うほど長女の性質を語っているかのうような発達障害についての動画を思い切ってお伝えさせていただきました。
それと同時に、療育だけでもさきに経験させてみたいと思い、医師に意見書を書いていただきました。
そして、まずは次女の通っている療育へ、現状の受け入れ状況と内容を確認し、長女に合うかかわりができるかをおたずねしました。
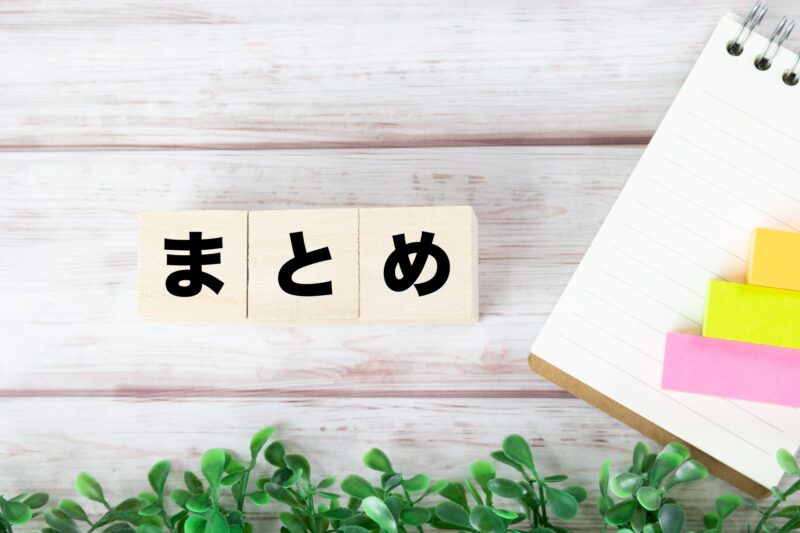
まとめ 現状と対応
まとめるとこういうことです↓
現状:長女の学校生活に、長女自身ではどうしようもない、コントロールできない困難さを感じているようだ。
⇓
対策:・状況把握のための心理検査(発達障害診断のための検査)
・学校での担任の先生のサポートを求める
・療育を受けるための意見を医師に書いてもらう
・社会生活をしていくにあたって根本的な課題にアプローチするための療育探し(見学)
現状としては長女も療育を受けられる体制を夏休み中に整えられるように動いています。
追記 長女の発達検査の診断
先述したように心理検査後、追加で医師から問診票を渡され、提出しました。
後日、医師との短い面談と確認があり、
結果、長女にもかなり強いASDスペクトラム症の傾向があるという診断を受けました。
実は、私は、その時の医師との会話で長女の現状をうまくとらえてくれていないという印象を抱いたのですが、診断名としてはそのように出ました。
この医師とのすれ違い感も、発達障害の子の子育てをされている方には意外とあるのではないかと思うので、後日記事にしていく予定です。
参考記事:ASDを調べる診断方法とは?診断テストや年代別のセルフチェックを解説|精神特化の訪問看護ステーション くるみのアトリエ(仮)

ここまで読んでいただきありがとうございました。良ければほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです! ※他のエピソードへのリンクは下へ↓
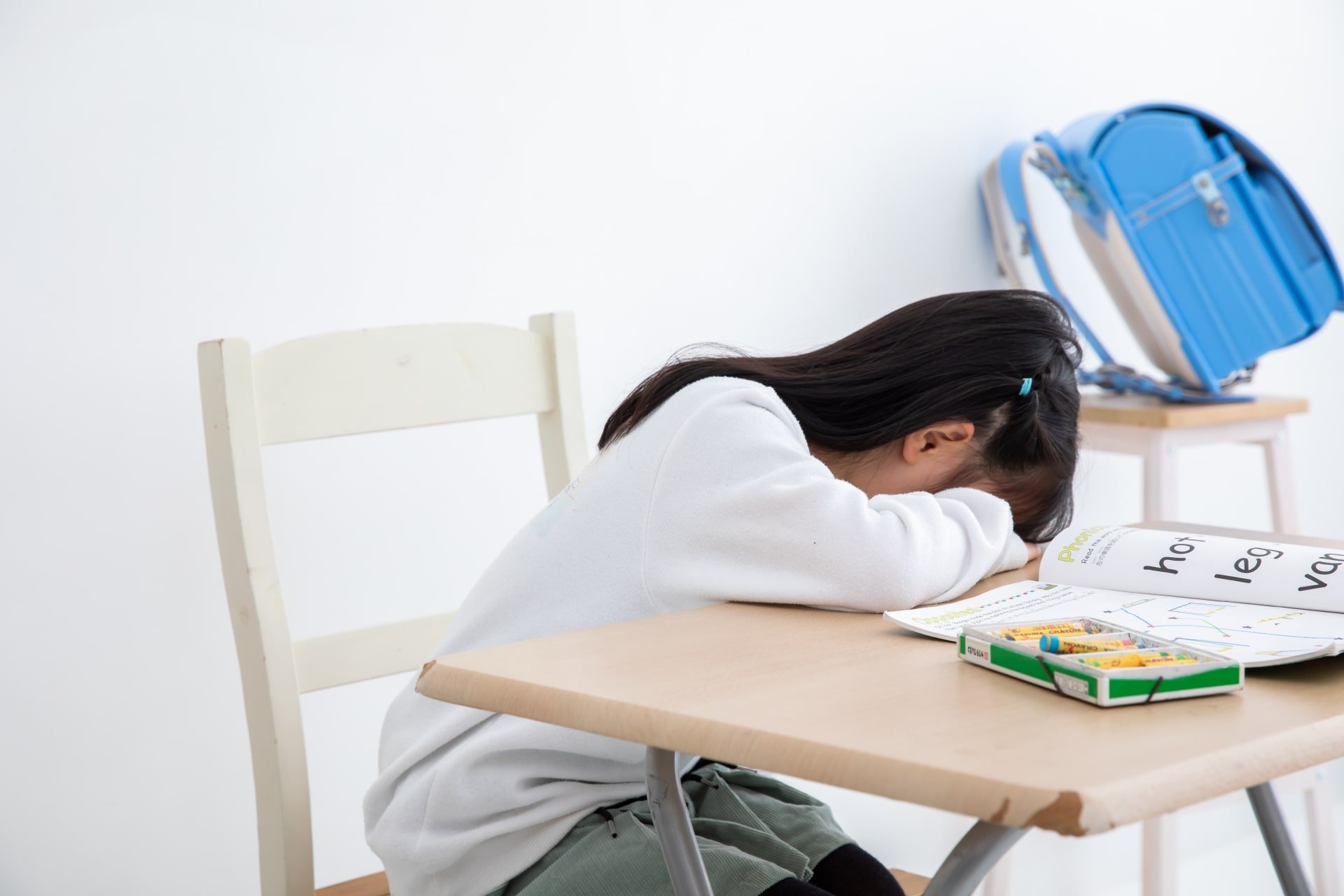







コメント