皆さん、子どもに寝る前の絵本の読み聞かせをされている方が多いと思いますが、お子さんはお話を聞きながらすやすや眠ってくれますか?
小学5年生になってASDの診断を受けた我が家の長女。長女についてのブログを書いていて、先日ふと思った事がありました。それは、そういえばうちの長女、おやすみ前の読み聞かせで寝たことがほぼない!!
思い返すと我が家では絵本を聞きながらすやすやなんて、奇跡のような光景でした。
と言うことで、この読み聞かせが聞かない原因について少し思ったことがあったので、今回はそのことについて書いていこうと思います。
覚醒作用!?お休み前の読み聞かせが逆効果だった長女

長女を寝かせるのはそれはそれは苦労をしました。次女も次女で私が離れると起きるのでこれまた苦労したのですが、次女は絵本を読んでいるうちに寝てくれていました。
ですが、長女は2回か3回しか読み聞かせ中に寝てくれたことがありません。
絵本を読んでいる間に寝ている長女を見た時はどれほど感動したことか!!
基本、夜はなかなか寝ない子だった長女。幼児期は夜はむしろ元気になるのか、ずっともぞもぞしているので、お腹の上で抱っこして、半ば押さえつけるようにして落ち着かせることに必死だった思い出がありますが、そんな感じだったので、絵本を読み聞かせられるような時期になった時は期待したものです。
ですが、おやすみ前の読み聞かせをするようになっても、むしろ、ますます寝ない長女。親の方が先に寝てしまうことが日常でした。仰向けで持った絵本を何度顔面に落としたことか…。

痛っ!!?
寝かせることがすっかり親のストレスになったまま長女は大きくなったわけです。
ADHDの注意散漫!?音や絵に反応して余計に覚醒!?

そんな日々を抜けて小学生中学年になった長女。このころから少しでもリラックスして寝られるように。と言う思いと長女自身のリクエストから私たちは寝る前のお話読み聞かせなどの動画でお話を流すということをしていました。もう小さい頃から寝ないことはははとしても常識になっていたので、とにかくベットに入るということのためにお話を流すということをしていたように思います。
もちろん、30分後、はは(私/はゆまーま)がお話を消し忘れると、11時頃になっても起きている。

しまった!!!
じゃあ、お話を聞かせなければいいじゃん!
そう思うでしょう。
その通りです。けれど、時間を決めているのに身につかず、永遠に寝る支度が進まない毎日と長女の激怒が度々挟まることで、もう、はっきり言って手段がわからん!!そうして寝る前のお話に頼っていました。
そうして長女が5年生になったある日、丁度ASDの診断後、やっと気づいたことが!!

これ、ADHDの不注意とか、音声や映像の刺激で過剰にアドレナリンが出るとかで寝られないのでは??
うっすら気づき始めてことあるごとにそうではないかと思いだすはは。
そしてある時、長女の幼少期のことが思い出されて「はっ!」としました。

あ!だから絵本を読めば読むほど寝ない現象が起きていたのか!?
もとより、読もうが読むまいが寝ない長女だったので 「長女 = 寝ない子」と思っているため気づかなかったはは。
物語からいろんな感情や語彙力を身に着けてほしい、寝る時も楽しい幸せな気持ちでいてほしい。
そう思っていた親心はことごとく長女を覚醒に導いていたということに気づいたのでした。
寝なかった原因
読み方
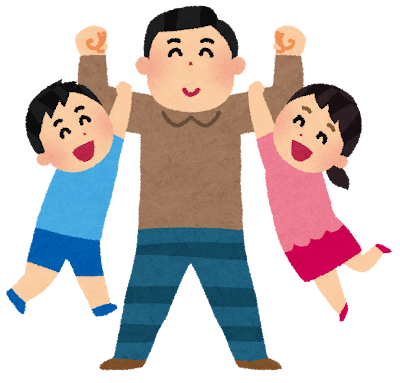
少し調べてみると、絵本を読んでいて寝ない子は、その読み方に原因があるかもしれないそうです。具体的には、抑揚のありすぎる読み方やお話の内容がアクティブすぎるなどの原因があるようです。
この点、我が家はかなり当てはまっていました。
我が家では、割とちちが子どもたちを寝かしつけてくれようとすることがよくあったのですが、ちちが絵本を読むと永遠に終わらないということがずっと起きていました。
それもそのはず、ちちはかなりの抑揚をつけて、キャラクターごとに変な声などの設定をして読んでいたのです。当然、子どもたちの脳はアドレナリンが大量に出ている状態。つまり寝ないどころかテンションが上がっていつまでも次の本を所望する。比較的読み聞かせ中に寝ることのできる次女もなかなか寝なかったのはそういうことかと納得です。
これはもちろん、ちちなりの”楽しくしたい”というわが子を思うがための行動なのですが、残念ながらやりすぎでした。
ちちの気持ちも十分わかります。
仕事から帰ってきて、一日のうちで唯一子どもと楽しく過ごせるタイミングです。とにかく子どもたちに喜んでほしい、楽しくしてほしい。愛情以外の何者でもない。それだけの想いだったのだと思います。
ですが、残念ながら、寝る前。
これは今もありますが、「夜だからあまりテンションをあげすぎてはいけない」という考えを、状況を見て判断することが苦手なのだなと思うことが日常の場面でよくあります。
この寝かしつけの絵本も同じくそうでした。
当時、寝かしつけを頼んだ際の私は、そうやって抑揚満点で変な声で配役をして絵本を読んでいるちちが、子どもたちが寝ないとしまいにはイライラして怒っている雰囲気を出してしまうことがわかっていた私は、「そのテンションだと寝られへんやろ」とか「2冊までとか決めて、求められるままに読まないようにすればいいのに。」「先に寝ればいいのに。」などと折を見て伝えていました。が、まさか、自分が愛情のためにしていることが逆効果だなんて思ってもみないちち。
ちちはただひたすら子どもがかわいくて、子どもに喜んでほしいことに全振りしているだけなのですが、それはどんどん悪循環を起こし、これから寝る子どもたちのテンションを上げてしまうのです。
私もそこまではっきりと言語化して認識してなかったため、今日までずるずる来てしまいました。

この点はASD同士の相乗効果とでも言いましょうか?我が家にはこの相乗効果で複雑怪奇になっている事例が多数発生しています。
参考:未来に種をまく ヨメルバ 「寝つきが悪く、本を6冊読んでも寝てくれません。」
参考:「早く寝てほしい」絵本の読み聞かせが終わらない2歳【専門家がアドバイス】
子どもの要求を断るができない 「おやすみ」の切り替え
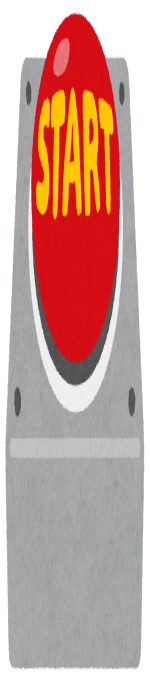
我が家のちちはASD傾向があります。
寝かしつけ中、子どもが「もう一冊読んで!」と言ったとき、ASD傾向の強い人は「断る」という選択を取るために頭の中で多くの情報を処理する必要があります。
「ここで断ると悲しむかも」「でももう寝る時間」「子どもが大切だから優先したい」「明日は学校だし…」と、複数の要素を一度に整理しようとするため、結果として判断が遅れたり、場当たり的に子どもの要望を受け入れてしまうことがあるようです。
また、我が家のちちはよく「優しい」と言われます。これは私も基本、ちちのいい面としてとらえてはいますが、このやさしさの出し方がASD特有の性質によって過剰になることがあると感じることがあります。これが寝かしつけの場面でも出ていると感じたりもします。
結果的に「状況の切り替えができない」ことにつながることにもなり、ことも立ちも「おやすみ」の切り替えを学びづらくなっていたと思います。
日中の適切な活動が足りていない
以前「ASD 長女の療育の効果 療育の最大パワー」と言う記事でも書いたのですが、長女はおそらく、その脳機能の特徴によって、適切なエネルギー循環が無いと日々を通常に過ごせません。
現状の様子でお話すると、いい循環ができていないと怒りやすくなったり、叫び声のような、うなり声のような声を発してそのモヤモヤと葛藤していたり、オーバーヒートして突然疲労感を現わして物事が進まなくなったり突然寝てしまったりします。
つまり、日中の活動量や内容が彼女の日常での頭の働き、メンタル、最終的には寝る時の状態にとても影響しやすいんじゃないかな?と感じています。
具体例としては、日中、学校生活での課題や行動が複数に重なり、何かができていないような状態、もしくは何とかついていっているけれど、とても情報処理を頑張っている状態に陥ると、とてつもない勢いでフラストレーションやストレスがたまり、脳に負荷がかかります。
そうして帰宅すると、ぼーっとしたり、常に怒っていたりするようになり、何を何度声掛けしても、可視化しても、サポートがなりたたない状態で日常生活が回らない度合いが一層上がるように思うのです。
そうなると寝るまでの流れもことごとく進まず、やっと寝られる状態になっても寝付くことが難しくなったり、寝ることができても起きてしまい、しかもしばらくの間は混乱状態で私たち両親に抱き着いて泣いているということもあります。
また、脳のコントロールがうまくいかず、エネルギーが有り余って寝る前にハイテンションになったり、寝る前にやる気になって覚醒状態になってしまうということも起こるように思います。
これらを防ぐためには身体のエネルギーバランスと脳のグルグルを解消すること。少しでも整理できる状態にもっていくことが必要かなと思います。
ある意味、寝る前の状態が、長女が今日一日どういう状態で過ごしたかのバロメーターになるな。とすら思います。
長女の場合、これについては今は療育での大好きな先生とのやり取りと楽しいと思える活動を通して経験できるたくさんの「できた」によってバランスが保てているところが大きいと感じています。
ですが、まだ発達障害というものを意識していなかった当時は時間や動きを習慣化しても身につかない。どうしてこんなに寝ないの?お話って睡眠導入に効果的なんじゃないの?と悩んでいました。
まとめ
子どもが寝ないと、睡眠不足で成長に影響があるんじゃないか、風邪をひくんじゃないか、自分時間が無くなってしまうじゃないか!なんていろいろ気がかりだったり、必要な時間が取れなくてストレスになったりすると思います。
今だから考えられる当時の子どもたちの状態。
それがその家庭の当たり前になってしまうので気づきにくいかもしれませんが、当たり前をそのままにせず、
その子の特性や状態を見極めて、現状に問題点は無いか?ほかに工夫できることは無いか?と考えていくとが大切だなと改めて思います。
これを読んでくださった方に、もし、子どもの寝かしつけに苦労されている方がいたら、何か参考になるものがあれば嬉しいなと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓







コメント