「日常ー学び」では日ごろの子どもたちの行動や発言とそこから学ぶこと、ちょっと笑える日常の会話などの息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
「日常ー学び」では発達障害を持つ子の子育てあるあるや、我が家の場合の発達エピソードについて、日ごろの子どもたちの行動や発言、そこから学ぶこと~ちょっとクスっと笑える日常の会話まで、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
同級生と遊べるようになった次女
友達とかかわる楽しさがわかってきた
放課後デイサービス、学校との共有で安定感が増していっている次女ですが、友達と遊ぶことは次女にとってまた違った意味が見えてきています。
一年生の頃はまだ幼稚園と同じようなテンポで、わが道しか行かないマイペース人だった次女も2年生になってしばらくすると、クラスでのコミュニケーションが増えてきて、特定の同姓のお友達に遊びに誘われることが出てきました。
ずっと友達と遊びに行くなんてことはしなかったわが子が、特定のお友達ができて、遊びに行くなんて!?と、私にとってもとてもうれしい出来事です。
そんな中で私が感じた変化があったので書いていこうと思います。
いい影響
次女が友人と遊ぶということをしだして現れたいい影響としては、友達と遊ぶ時間を取りたいから自分で宿題を進めようとすることが出てきたということです。
さらにそのことで全体的にやる気になる時もでてきて、比較的、ご飯や準備、お風呂など日常生活のすべてにおいて以前には比較にならないくらいスムーズになってきています。(以前が全く進まなさ過ぎたということなのですが…。)
また、日常の生活面での時間の進め方が少しずつ改善されていき、ますます友達と過ごすことに時間が使えて経験が積めるようになったことで、会話をする(相手の問いや呼びかけに反応できる)ことができるようになってきています。
次女の日常がどれだけ回らなかったのかわかる記事はこちら↓
困った影響
一方、人とのコミュニケーションが取れるようになると、それはそれで悩ましい現象も引き起こされています。
お友達とのコミュニケーションが増えてくると不満に感じることも増えてきて、とても怒ることが増えてしまったのです。
次女がお友達へ怒る理由として、私が見聞きした範囲では
- 友達が驚かせてくる
- 追いかけてくる。 ※次女は驚かされること、追いかけられることが何よりも嫌いです。
- よくないこと、危ないことをしているから注意をしたのに聞いてくれない。
- 鬼ごっこをしている最中に、鬼の立場で追いかけるつもりなく話しかけたのに、聞かずに逃げられた。
※以前は鬼ごっこは追いかけられるから問答無用で断っていた次女からすると、鬼ごっこに参加するようになっただけとてもうれしいことですが。

いや、それは鬼だから逃げるよ…。
他にも…
- ローラー付きの靴を友達にかしてもらって遊んでいたら、転んでしまったのに誰も気にしてくれなかった。
- また、同級生が遊んでいる途中でけがをして、我が家に応急処置をしてほしくて次女と一緒に訪ねてきた際には、
「もうちょっとで帰る時間なのに!なんでそのまま帰らないの!?家も近いんだから、帰って絆創膏を貼ればいいじゃん!!」と謎に怒っていたり。
いやもう、最後のに関しては、なんで友達がけがをしたことを心配するのではなく、悪態つくんですか!!
自分がケガしたら大泣きで一大事じゃないですか!?
転けて気にしてくれなくて怒っていたのはどこの誰ですか!?
と、いろいろ突っ込みつつ…。
次女は次女なりに、はは(私)に迷惑をかけているのではないかという思いが優先されてしまった結果ではないかとははの反省するところでもありました。
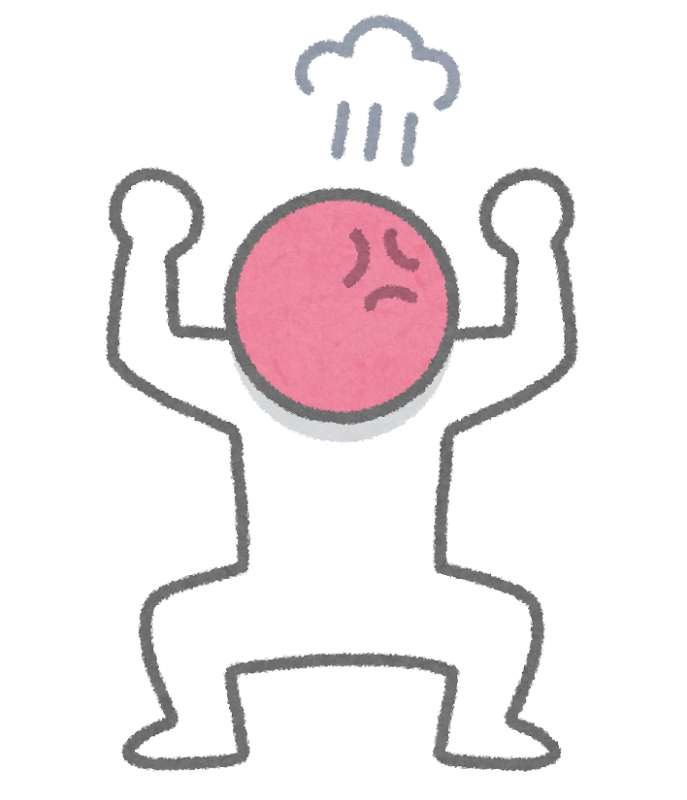
さて、ブログを始めたきっかけ ~発達障害との出会い~という記事にも書きましたが、
次女はもともと小さい頃からよく怒る子でしたが、小学2年生にもなると、自分ルールが一層強く確立されてきました。(私が、次女の中ではよく感じるASDの特徴だなと思うところです。)
そこに引っかかると、納得できるまで怒りが収まらない、しかもそれを圧倒的に相手だけの問題だと思ってしまいがちです。
そこへきて、相手も同年代、そのことを順を追って説明してくれる先生のような大人ではなく、まだ、楽しいことを優先して動いてしまう年代だと思います。
次女の言い分が正しかろうが、間違っていようがお構いなしなことも多いのは仕方なく、融通を一切きかせられない次女も仕方なく…。話を聞いている親も状況を見たわけではないので判断しがたく…。
日に日に、怒る → 憤慨 に変化していく次女の様子に、このままだと悪化するばかりだと頭を悩ませていました。
ひとまず、担任の先生に学校でのその友達との様子を伺うと、学校では問題なくとても仲がいいそう。

次女は学校から帰宅すると、”ふんがい”なんてかわいらしい感じじゃなくて、まさに漢字で書く”憤慨!!”がぴったりの激怒具合でした。
幸い、いつも声をかけてくれるお友達を見ていても、とても次女のことを好きで遊んでくれているのがわかったので、これは本人たちの問題でもあるし、と傍観していました。
けれど、そのうち次女が「〇〇ちゃんは学校だと嫌なことをしないけど、外で遊んでるとしてくるから遊びたくない!!」と言うようになりました。
そうして憤慨しながら遊んでいるうちに、懸念していた通り、みるみる次女のストレス値が上がってきて、生活面でも愚図りや引っかかりが多くなってきてしまいました。
その友達に対しては、遂に、顔を合わせると相手に直接ぶつぶつ文句を言い始める始末。外でも友達に大声で起こりだすことが出てきました。
ここで難しかったのは、わたしもできれば遊びたいという次女の気持ちです。
遊びたいけど、また嫌な気持ちになるかもしれない。葛藤はあるものの、結局遊びに行きます。
そして、憤慨して帰ってくるのです。
私としてもいろいろ思うところはありましたが、私には次女が彼女なりにそんな自分や友達をどうにか受け入れたいと頑張っているように見えていたので、後から愚図りが増えたとしても、本人に任せるようにしようと思いました。
幸いだったのが、そんな状況にもかかわらず、お友達は相変わらず一緒に遊んでくれていたことでした。
お友達は、自分がやりすぎたと思う時は自覚して謝りに来るのですが、次女は好き放題怒り散らしていて、自分が謝らなければいけないときにどうしても謝りにいけない状態もおこりましたが、少しずつ気を付けるようになってきている様子は伺えたので、次女なりに考えて反省し、怒りを抑える、または切り替える工夫を少しずつしようとしているのかなと思っています。
その後もお友達へのぶつぶつ文句はしばらくたえなかったのですが、次女の中でも徐々に考えを整理することができたのか、ずいぶん長くかかりましたが、学年も上がり、最近になって少しずつ、ただ楽しく遊ぶ術を身に着けられてきたように思います。
3年生に上がった今は憤慨して帰ってくることも少なくなってきて、見た範囲では楽しく遊んでいる印象です。
ややこしい次女の状態に付き合ってくれたお友達には本当に感謝しかありません。
そういうことを経て、今は多少嫌な思いをしてもまた外へ出ようと思う積極性が出てきたかな?という印象です。嫌なことが起こっても、折り合いはつけられる範囲だし、それに優る楽しいがあることに気づいたのかな?と期待を込めて思っています。

同級生とのコミュニケーションが課題
次女にとって友達と遊ぶことは楽しいことであり、不満、怒りが増えることでもある
友達と遊ぶようになって、子どものうちは特に同級生とのコミュニケーションが課題なんだなということが見えてきました。
大人との関係では、本人もきちんとしなければいけないと思っているのか、ある意味距離感が意識出来て良好です。
あるいは、本人の学習してきた人というものの範囲からそれほど外れていないから不満も感じにくいということなのかもしれません.
ですが、同年代では距離感がある意味とても近くなってしまったり、本人の学習範囲に収まらないイレギュラーな動きなどに触れることが多くなって、接し方がわからなくなっているように思えます。
発達障害、特にASDの特徴としてあげられる自他境界(他者が自分とは違う考え方を持っていること、物理的に違う個体であることの認識)があいまいであることや中枢性統合(個々の体験、情報を統合して物事を把握していくこと
)が難しいためなのでしょうか?
子どもたちの中は大人よりも一層、まだ整っていない社会なだけに、その弱さを持つ子どもにはとても恐怖の塊に見えるのかもしれないなと感じたりもします。
そのために、同年代の子と接する機会が増えることで不満がとてもたまりやすくなっているように感じます。
そして次女の中に、不安、マイナス思考、正義感、固定観念、そこを曲げられない不自由さをとても感じます。
が、こればかりは、少しずつ経験測で自分の対処法を見つけていくしかないと思います。
経験しながら、いろんな考えの人がいることを知って、それに対する対処法を彼女のなかで見つけていけるようになっていってほしいと思います。
なので私としては、次女の感情を一つの考えとして受け入れること。
その時々の状態と次女の気持ち、対応をきいて、コミュニケーションがとれる心的状態をに保つこと。
そのうえでいろいろな考え方がある、こう思ったのかもよ?こういう風にも考えられるねといった例を伝えて、少しでも次女に考え方は人それぞれだということ、幅をもった考え方の練習をすることをサポートできればいいなと思います。
次女がどこまでそれを受け入れられるようになるかわかりませんが、もう少し大きくなって、自分の特性や苦手なことを理解できるようになってきたとき、いざという時に次女とコミュニケーションを取れるようにしておこう!という親の心構えも必要かな?とも思いました。(簡単なことではないと思いますが…。)
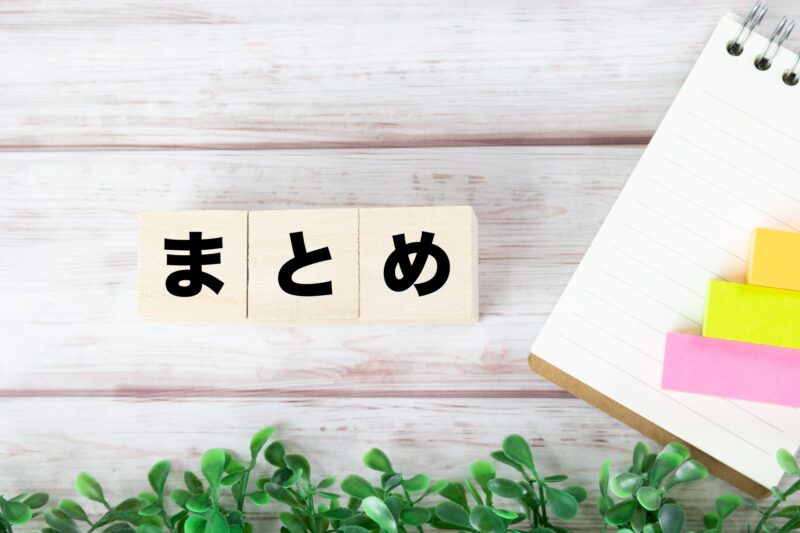
まとめ ~友達と遊ぶことから見えた、今私ができること~
私が、次女の友達関係の中で思ったのは、理解ある人に触れる機会を多くする(親、放課後デイサービス、学校の先生)ことで安定することも大切ですが、そうでない人にあう影響(同年代のお友達と親しくする)も大切なんだなということです。
次女は放課後デイサービスを気に入って毎日行きたい!!と言いいます。放課後デイサービスの方も、「増やしますか?」と次女の希望に合わせてくれようとしてくれます。
実際、週1回から2回には増やしましたが、友人と遊ぶことで得られる感情は次女には必要なことだと思った事で、ただ居心地のいい環境を増やすことだけがこれからの次女を支える経験になるわけではないと感じました。
現状、友達と遊べる日、姉妹で遊べる日、も考慮してバランスを取っていきたいと思っています。
自分への理解をしようとしてくれる環境と、そうでない環境、それぞれの相互作用を鑑みて療育を利用することが大切だなと感じた出来事でもありました。





コメント