「日常ー学び」では発達障害を持つ我が家の姉妹のエピソードや、そこから学ぶことと、ちょっとクスっと笑える日常の会話など、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
長女は5年生でASDの診断を受けました。(診断はASDですが、私は、ADHDの要素と複合して長女の困りごとが出ていると思っています。)
その日常を見ていると、長女にはスイッチがあるのではないか?と思います。
スイッチが入ると簡単な呼びかけで日常生活を回すことができるのですが、残念なことにこのスイッチ、ほとんどオンになりません。
昔はこのスイッチがたまに入ることで、「わかってるし、できるんだよな~?」と、発達障害に気づけず、ずいぶんと疲弊しました。
さて、長女は5年生になって過度な疲れとオーバーヒート状態が目立つようになっていました。これはいけないと、夏休み中に長女の療育(ここでは放課後デイサービスのこと)を開始しました。
実はそれが今のところ、長女にとってとてもいい効果を発揮しています。
↓↓我が家の療育選びの話はコチラ↓↓(よかったら合わせてご覧いただけると嬉しいです。)

今回は、療育をはじめたことで長女のやる気スイッチの条件が見えてきたように思ったので、我が家の場合の長女のやる気スイッチの条件について考えていきたいと思います。
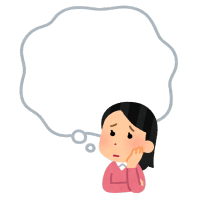
わが子にはどうも極端なやる気スイッチがあるな?
と感じている方の共感の場や、発達障害の子育てを考えるきっかけになれば嬉しく思います。
↓↓この記事はこんな方に読んでいただきたいです。↓↓
・子どもが気分屋で日常生活に困っている。
・子どものやる気スイッチを押そうと毎日奮闘している。
・家庭外の療育を進めるか迷っている。

スイッチの条件に気づいたきっかけ
小学5年生になった長女が、宿題ができなくなり、忘れ物も多くなって
「完全に脳がオーバーヒートしている」
そんな印象を抱き始めた頃、はは(私/はゆまーま)は一つの可能性に目を向けました。

もしかして、長女は結構な頻度で成功体験を繰り返していく事で、やる気スイッチが入りやすくなるのでは?
そう思ったきっっかけは、オーバーヒートになりがちな5年生の日々にも、体験学習などの大きいイベントがあった際には「副班長になったの!」とやる気を見せたり、その前の学校行事でも「班長をする!」と意気込んでいる長女の姿を見ていたからでした。
試しに、休日にお手伝い(食器を洗う、カレー作りやお味噌汁作りなどを手伝ってもらう)などをお願いしてみ
ると、やっぱり長女は一時的にやる気に満ちるのです。
それでまた、宿題ができる、、、とまではいかないものの、やろうという気持ちまでは出たり、いつもは時間を気にすることができない長女ですが、時計を見て時間を気にしようと頑張る姿を少しだけ見ることができるのです。

これはアプローチの方法があるかもしれない!
と思いつつ、夏休みに突入して始めた長女の放課後デイサービス(以下、放デイ)探し。
すると、偶然、土曜日の利用時には、外出していろんな体験をさせてくれる放デイと出会いました。

これは、長女にとてもあっているんじゃないか?一度利用してみて、長女が毎週のイベントに負荷が大きのか、程よい成功体験になって整ってくるのか、様子を見てみよう!
そうやって放デイを決めました。
長女の初の放デイは初日からイベントで、博物館へ行くことになりました。

さて、どうかな?
初日から初対面の人たちと、初めての場所に行く事が、長女にとってどうなのか。少し不安ではありましたが
やってみるに越したことは無い!と、帰宅を待つはは。
そして帰宅してきた長女を見るなり、はは は半ば確信を持ちました。
長女は何とも楽しそうな満面の笑みで帰宅したんです!

やっぱり、この子は体験することが合っているのかも!
少し余談ですが、同じASDの診断を受けいている次女は、外出が嫌いです。
普段は公園で遊ぶこともありますが少しずつ減ってきています。友達に誘われても、予期せぬ事態(ボールが飛んでくる、人とぶつかるなど)を嫌がって行く事を渋ったりすることは珍しくありません。
また、遠足などの行事は基本前向きに見えますが、やっぱりストレスが多いのか、帰宅後は愚図りやすくなったりします。
↓↓次女がイベントがストレスになる話はコチラ↓↓(よければご覧ください♪)
一方、長女の方は、本当にイベントを楽しんで、帰宅後も「できた」報告や褒められた報告を嬉しそうに話してくれるという違いがあります。先述のように、イベントに向けての役割決めでも積極的です。
そんな違いのある姉妹なので、対応が全く違って翻弄されるははなのですが…。それはさておき、
今回の様子を見ていると、やっぱり長女は体験が向いているみたいだと感じます。
さて、話を戻して、楽しい放デイ初日を過ごした長女ですが、ただ、さすがに初対面の子どもや大人たちとの外出は長女にそれなりの疲労はありました。それは当然、誰でも疲れる状況だと思います。
帰宅後、前日に途中までしていた夏休みの課題の読書感想文を、珍しく
「読書感想文やる!!」
と自らやる気満々で机にスタンバった…はいいのですが…爆睡。
初めて、長女が机に突っ伏して爆睡している姿を見たはは。(基本、幼児期から昼寝はしない長女です。)
その後、一度起き上がって私のもとに来ると、そのまま床でまた爆睡。
こんなに長時間、疲労感満載の顔をして爆睡をしている長女を始めてみるはは。

いきなり初めてがたくさんのことをしたからね、不安もすごく大きかっただろうし、楽しかったけど、疲れたね。よく頑張ったね!
爆睡長女の疲労困憊の寝顔に、賞賛を送るははでした。
長女のやる気スイッチの条件
そんな出来事がきっかけになって、長女のスイッチをいかにスムーズに入れてあげられるかが長女自身にとってとても重要なことと、そのために必要な条件がわかってきたはは。
前置きエピソードが長くなりましたが、ここからは私が感じる、長女のやる気スイッチの条件をまとめていきたいと思います。
1つ目 細かい頻度で「できた」を体験すること
2つ目 「できた」を親や先生と共有すること
3つ目 落ち着いていること、考える時間があること
4つ目 自発的に「できる」と思える状態を保つこと(1.2.3の循環)
1つ目 細かい頻度で「できた」体験をすること
例えば学校行事も、その目的は体験を通して「できた」を積むことだったりすると思うのですが、長女の場合、これを割と細かい頻度でする必要があるのではないかと感じています。
それも、家事の手伝いなど、日常的にできることと、どこかへ行く事など少し大きい体験の両方を結構なハイペースでする必要があるのでは?と思うのです。
そう感じる理由は、長女の興味が持てないとどうしてもできない気質にあります。
発達障害としてはADHDやASDの実行機能の弱さに当たる部分です。
実行機能の弱さとは、行動の判断や欲求の抑制をつかさどる脳の機能が働きにくいことで、長女はまさにこれによって振り回されているという印象を、私はもっています。
具体的に、実行機能に弱さがあるとどういう影響があるのかと言うと、宿題ができないなどの「先延ばし癖」や、この記事のテーマである「スイッチが入らない=やる気が出ない」そして常に自分が今興味を惹かれていることに行動を移してしまう。と言うことが起こり、これらが自身でコントロールできない状態を抱えます。
↓↓宿題ができない長女の話はコチラ↓↓(よければご覧ください♪)
ですが、長女を見ていると、それと同時に逆にやる気スイッチを入れることに興味を持ちさえすれば好き嫌いではなく取り組めるのではないかとも思うのです。
例えば、勉強が嫌いでもスイッチが入ればとても楽しく集中できますし、無謀な計画だとしても(時間間隔が無いのでたいてい無茶になる)自発的に計画を立てて進めようと意気込みを見せてくれます。
一方、スイッチを入れる気にならなければ、いつもしていることや得意なこと、本来なら楽しんでできていることなども、「わかっているけどどうしてもできない。」ということになり、ましてや「これは今日終わらせるものだから頑張らないと!」と意志をコントロールすることはとても難しいように思います。
というわけで、はは は、この長女の実行機能の弱さにアプローチするためには、何よりも本人のやる気を引き出すことが重要だと感じてきました。それも常にその循環を保つ工夫をすること。
それはつまり、長女自身がスイッチを入れること自体に興味を持つことが必要で、スイッチが入った時の楽しさを繰り返し体験すること、その環境を整えることが重要なのではないかと言うことです。
今回の放デイでは、長女が放デイの先生たちをとても好きになってくれたこと、イベントを楽しみにして参加できることでスイッチが入りやすくなった上に、体験を通して「できた」を毎週感じることができ、スイッチが入る。そしてさらに「できた」を経験したいと自らスイッチを入れることに興味を持つようになることにつながるのではないかと思います。
2つ目 「できた」を親や先生、理解のある大人と共有する
1つ目の「できた」の体験をした後は、できるだけ、共有できる大人がいる方がいいと感じています。
それもできれば複数いるとよさそうです。
これは単純に次への意欲になることと、その体験やポジティブな感情がより本人の記憶に残るからではないかな?と思っています。
長女の行っている放デイの様子を見いていると、恐らく、その「できた」を一つ一つを拾って、一緒に喜んでくれる大人がいて、それをまた帰宅後に、親とも共有して一緒に喜ぶことができているように思います。
さらに、共有する時はできるだけ本人に理解のある大人である方がいいと思っていて、返答に、「すごい」や「偉いね」と言う定番の返しではなく、”一緒に喜ぶこと”、”何がどういいと思うか、プロセスなどに触れてよりできた体験を深めてあげること”がとても意味のあることになってくると思っています。
そういう意味で、発達障害に理解のある大人に適切にアプローチしてもらうことが望ましいと感じています。
これがより長女の心を満足させて次の「できた」をプロセスも含めて求める意欲になっていくのではないかなと思います。
3つ目 落ち着いていること、考える時間があること
長女を見ていると脳内多動があるように思います。(あくまでははの意見です。
毎日脳内がぐるぐるしていて落ち着かないんだろうな。と、どうしてあげたらいいのか考えあぐねてきたははなのですが、
興味の持てることに触れた長女は脳内の興奮様態が少し落ち着くように感じています。
まるで混沌とした頭の中が、興味の対象を見つけることで「これについて考えればいいんだ!」と進む方向を見つけて安心でもしているようです。
こうやって、落ち着いて考える時間が生まれる。
ははとしては、この時間を感じとって、放っておいてあげることも大切ではないかなと考えていて、長女が「なんかぼーっとモードに突入している!」とその雰囲気を感じ取った時には極力そっとしておくようにしています。
たまに怖いくらいぼーっとしている時のある長女ですが、この時間を大切に見守ることで、頭を整理する、自分でいい循環癖がついて、自分のコントロール方法を見つけて行けるヒントになるのではないかと感じているところです。
4つ目 自発的に「できる」と思える状態を保つ
そして、これが一番大切ではないかと感じることが、1.2.3の適度な繰り返しです。
適度なと言うところにポイントがあるのですが、先述の通り、長女の場合はこれが結構な頻度で必要なのではないかと思っています。
理由は、長女は定型発達(発達過程において平均的な発達を示す人々のこと)の子よりも「できた」体験への興味が薄れてしまいやすいように感じるからです。
脳内多動によってか、不注意(すぐに他の興味のあることへ気がそれる。)によってか、ワーキングメモリによってか?長女は極端にやる気につながる成功体験を思い出しにくいように思うのです。これもまさに実行機能の弱さなのだと思います。
だからこそ、「できた」を忘れないうちに繰り返していく事が重要なのではないかと考えています。
長女にとっては「できた」を忘れないうちに繰り返すということが自発的に「できる」と思える状態を保って、できることに興味を持つことができるのではないか。と、感じているところです。
大切なのはその子にとってのいい循環を見つけてあげる
長女の件で思うことは、極端なスイッチを持つ子は本人もそのスイッチのオンオフに踊らされて困っているのではないかと言うことです。
実行機能が弱いことはとても厄介です。
ははとしても長女に対しての子育ての悩みの半分以上はここに集中しているのではないかと思うほどです。
今回、長女のやる気スイッチについて考えることで、我が家の長女の場合は、
・大小の「できる」体験とその適切な共有
・それをストレスがかかりすぎない頻度の様子を伺いながら、比較的頻度高めに繰り返していること
が必要ではないかと思いました。
発達障害とひとくくりに言っても、個々によってさまざまな子どもたち。
なにも、発達障害と言わなくても人間とはそういうものだと思います。
ただ、その困難を経験する人が多いか少ないかと言う問題で、大衆意識の中では認知されていないというだけだと私は思います。そんなことって、たくさんあるのも事実だと思います。
大切なのは、その子がどういう状況で、何に困っていそうか、どういうことに喜んで、どうすれば本人も楽しくその気質をコントロールできるのかなのではないかなと思っています。
自分のお子さんに合ったアプローチに日々悩んでいる方の参考になれば幸いです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓







コメント