「日常ー学び」では日ごろの子どもたちの行動や発言とそこから学ぶこと、ちょっと笑える日常の会話などの息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
爆泣き!でも成長したね!!インフルエンザの予防接種
今回はインフルエンザの予防接種でのお話をしようと思います。

結果としては、次女が院内にてギャン泣きからの激怒!
来年は鼻から噴霧できるフルミストタイプをオススメされ、私もフルミスト宣言して帰ってきました!
徐々に迎えるインフルエンザの予防接種当日
いよいよ予防接種の日が一週間後に迫ってきたある日。
直前に伝えて恐怖に駄々をこねられると大変なので、子どもたちには一週間前からと前日、当日の朝にインフルエンザの予防接種があると伝えていました。
長女はすんなりと了解をしてくれますが、次女はきちんと納得がいくように説明を繰り返さないといけません。
前日や当日に言うとプチパニックで愚図りだします。
説明の時間を重ねる必要があることと、次女自身にも向き合う時間が必要なので、一週間前には一度、伝えるようにしています。
ただ、あんまり言いすぎても恐怖がこみあげてきますし、気分が不調の時に言ってもしばらく収集がつかなくなります。
言うタイミングと話すテンション、当日までの伝える回数に気を遣うははです。
その甲斐あってか次女は徐々に行く覚悟ができたようで、当日の朝は元気よく「うん!」と返答。
それはもう、あれ?予防接種って何か知ってたっけ?と言いそうになるくらいすんなりと元気のいい返事を返してくれました!
二人とも早く帰ってくるようにと目標の時間を指定して学校へ送り出します。(二人とも時間間隔がないので連絡帳に書いて、前日用意をしているときと朝出る前に確認!)
この一週間、時折、予防接種へ行くのだと思い出しては「嫌だ!」言い出すこともあった次女でしたが。ご機嫌で帰ってきた姉妹。

「おお~!時間通りに帰ってこれたね!」
いざ!予防接種へ!!
長女は前年もそうでしたが、今回はさらに自分をコントロールしていて、(次女に怖くないよと示したかったのかもしれません。)自ら椅子に座って一人で受けられました!
さて、次女はというと。
どうやら必死に冷静になろうと脳内葛藤中。
椅子まで二歩くらいの距離。
椅子へ向かう心の準備を整えている。
…..ところに看護師さんが二人強制乱入!
次女が葛藤している時間を許さず、問答無用で固定にかかります!
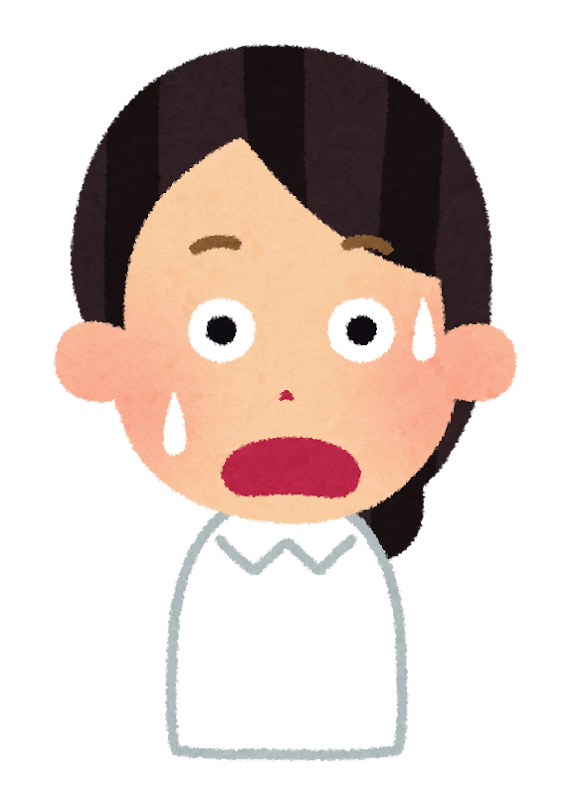
さあ!脳内葛藤に時間のほしい次女は大混乱です!!
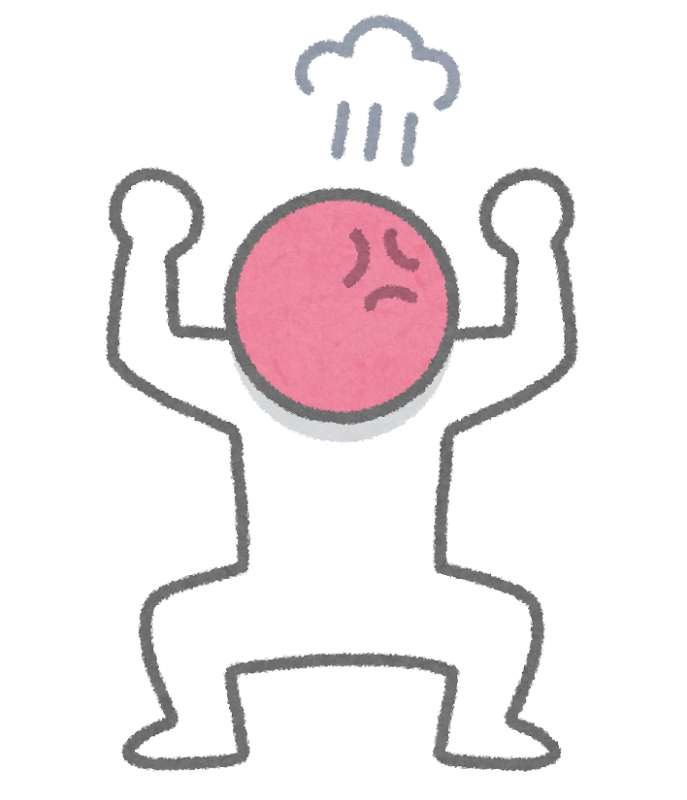
一回目の大変さを知っていて、構えているであろう看護師さんの気持ちになると、そうなるだろうなと理解はしつつも、次女は今世紀最大に頑張っていることが分かった はは。

この上ないくらい頑張ってるのにな…。
すると…
「ちょっとまって!!自分でいく!!」 次女が叫びました。
落ち着いて頑張ろうとしている気持ちが、ありありと伝わってきた、決意の込められた一言!!
に、はは には聞こえたのですが…。
「うん! 行こうか!」 と連行しようとする看護師さん。
きっと、次女にとったら頑張って自分で行くと伝えたのに、聞いてもらえなかったことで絶望してしまったのでしょう。ますます大混乱です!
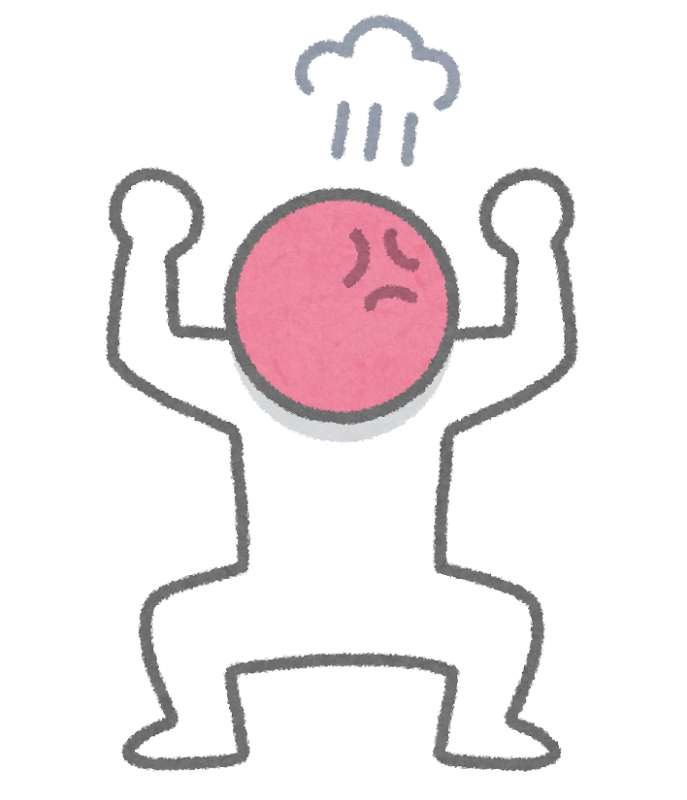
「お!自分で行こうか!」と応援する はは(自分の意志で行かせてやってくれと思いながら)
でも看護師さんにつかまれて恐怖に支配されてしまっている次女は暴れ続けます。
看護師さんとしては次も控えているし、必至だったのだと思います。
それはわかるので、どうしようかと ははも迷いながら
「そやね、自分で行くね、自分で行こうね。(看護師よ!気づいてくれ!)」と声をかけるしかできず…。
もはや、誰かが自分の体に触れていることが恐怖でならない次女はさらに大暴れ。
「じゃあ先生が行こうかな~?」と先生。
結局、無理やり打たれてしまった次女。
診察室を出てから激怒して、私が近づくことも嫌がってしまいました。(多分誰にも触れてほしくない)
長女の神対応
診察室を出た私たち。
長女は、頑張ったのに悔しさと恐怖を抱えて出てきた次女に、一生懸命声をかけてくれて、触れないけど次女を包むように手を伸ばし、近くに立っていてくれていました。
すると、次女も少しずつ落ち着いてきます。
しばらくその様子を見てゆっくり声をかけながら、落ち着いてきたタイミングで、ご褒美にもらったシールに意識をそらせつつ「おいで」と手を伸ばす はは。
「いらない?」と手を引っ込めるとかすかに首を振る次女。
「じゃあおいで」
1.5メートルくらい離れた距離から、蟻の速度で歩き出す次女。
それに突っ込みを入れる はは。
蟻の速度の間で少しずつ機嫌を整えながらやってきた次女を「頑張ったね」と抱きしめるしかできないははでした。
対応することの難しさ
「一度手を放して自分で行かせてやってくれませんか?」そういえばよかったと帰宅後に反省しました。
でもそれだとかなり時間がかかってしまったであろうことは明白な事実でしょう。
後も控えているし、こういう時は難しいですね。
発達障害だけではないでしょうが、小児科や専門の知識が多少ある医師のいるところでも、とっさの判断が難しいことって多いなと思う日々です。
でも、今世紀最大に立ち向かおうとした次女!!
はは はそれを心から嬉しく思ったことを折に触れて伝えていこうと心に決めるのでした。
そして、本気出した長女の思いやりのある対応も、深く感動と賞賛!!
はは の感動を伝えました!
周囲の目
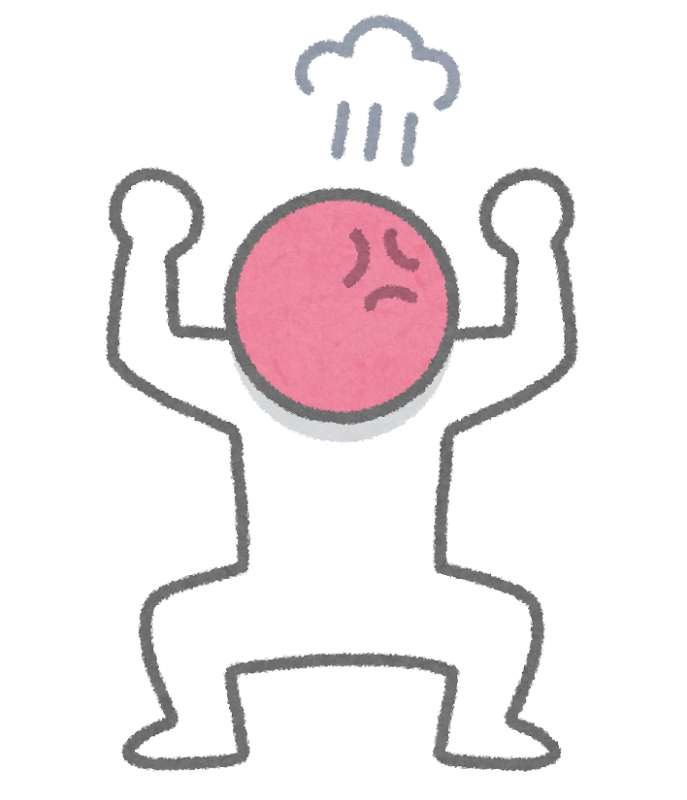
ところで…
子どもが外で激しく怒ったり、暴れたりしてしまった時、皆さんはどうされてるのでしょうか?
今回はいつもお世話になっている小児科で、待合も一組か二組が診察室を行き来している程度だったこともあって、私はある程度見守るという選択を取りました。
が、通常は混雑していることもよくありますし、小さい子もいます。
次女は時折、地団駄を踏みながら怒っていたので、放っておくと当たり前に周囲に迷惑になってしまいます。
親としてはすぐさまやめさせたいところです。
こういったシチュエーションは子育てをしていると少なからずあることかもしれません。
切り替えが苦手
発達障害の特徴に”切り替えが苦手”というものがあります。
この要因としては、自分の気持ちの理解や言語化が難しかったりして感情のコントロールをできないことや、急な環境の変化、予定変更などが苦手なことなどがあるようです。
次女でいうと、一度怒ると切り替えが難しく、そのうちに混乱してしまって何に怒っているかわからなくなり、ついには怒るという行為が目的になってしまっているようなことがよくあります。
次女の場合の対応
次女が怒っているときの様子を見ていると、その時の気持ちに反することや、少しでも違うと思うことをぶつけられると、そこにもどんどん不満や怒りを募らせてしまうように思います。
こうなると、本人をさらに混乱させる=さらに怒るといった感じで、よくわからないけど、とにかく怒りの感情は収めることができない!という状態になるのではないかと感じています。
こういう時、私はひとまず怒らせておいて何に怒っているのかを聞いた方がいいのかなと思います。
そして理由を話してくれた場合はそれに共感したり、共感できなければ「こう思ったのか」と内容を繰り返します。
すると、最初から諭したり急かしたりしているときよりも早く落ち着いてきます。
少し落ち着いてきたタイミングで、状況に応じてさらに共感したり、こういうこともあるかもしれない、とか、お母さんはこう思ったとか、ほかに考えられることがあれば、それを一つの考え方として伝えます。
ほとんどが否定して愚図りなおしてきたりするのですが、最初から諭す、怒るよりはましです。それに、次女は自分の腑に落ちるとすんなりと聞いてくれることもあります。(たまーにですが)
そしてこれは私の心持ちとしてですが、その時わからなくても大人になるまでに自分の感情コントロールのヒントのための蓄えになればいいかな?くらいの気持ちでいるようにしています。
まずは考え方にはいろいろあるということを知ってもらえればいいかなと思います。

とは言え、心がけていても余裕のないときはできない はは です。
今回のことで言うと、次女はそれはもう激怒で、私に触れられることすら嫌がっている状態でした。移動させることもできません。
無理に強いてしまうと激怒と聞かない状態が加速します。
怒って動こうとしない次女を少し離れたところから黙って見ている母。非常識に思う方もいるのではないかと思います。
けれど、こうも思いました。こういう時、周囲を気にして次女を気にできなければ、次女の不安や不満、被害者意識はさらに拡大して、マイナス思考の体験を重ねていくことになるのではないか?と。
そしてそういった体験の積み重ねが、できたかもしれない小さな成功体験も、してみよう!したい!と思う努力や工夫も台無しにしてしまうことになるのではないか?と。
子どもの成長のためにも発達障害を知ってほしい
外ではついつい周囲の目が気になることがあると思います。
が、発達障害といわずとも、子どもというのはいろんな特性があると思います。
子どもを育てる立場として、できるならば子どもの様子を真剣に見て、その子自身への対応を第一にしてやりたいと思います。
そしてそれは、発達障害の困りごとがある子どもたちには特に、不安感を和らげて、今後の子どもの人格や感情コントロール力を養う可能性のための土台に関係してくるのではないかなと私は思います。
他人の理解を得にくい言動や行動について、視野を広げる一つのヒントとして、発達障害という考え方はとてもいいものだと私は思います。なんでも発達障害というくくりにするためではなく、人としての視野を広げることのためにこの考え方を使いたいと私は思います。
周りを第一にしないことを見守ってくれる人が、そのための知識が、広く浅くでいいので、できるだけ多くの人に知ってもらえるといいなと感じています。





コメント