「日常ー学び」では発達障害を持つ子の子育てあるあるや、我が家の場合の発達エピソードについて、日ごろの子どもたちの行動や発言、そこから学ぶこと~ちょっとクスっと笑える日常の会話まで、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
今までこのブログは主にASDタイプの次女の子育ての日常から得る学びをテーマにして書いていますが、今回は長女の癖について気になったので書こうと思います。
調べてみてもあまり出てこなかったので、発達障害に関連することが引き起こしがちな癖なのか、そもそもこういうものってよくあることなのか?わたしにはわかりません。
なので、ある!!という方は何となく共感していただければ嬉しいかなと思います。ないという人は「へぇ~」と、こういう人もいるんだなというお話の一つとしてとらえていただければ幸いです。
因みに長女に関しては先日、ずっと気にかかっていた脳の得意不得意のヒントを得るために、発達検査に行ってきました。
結果としては長女には発達障害の診断は下りなかったのですが、はは (私)としては長女のほうが向き合い方が難しいと感じていること、長女も彼女自身の発言から日常的な問題を抱えてるようだということもあり、日常の困りごとを減らすために向き合う必要を感じています。
発達検査はこれについてのヒントとしてとても役に立ったので、検査してとてもよかったと感じています。
そのことについては別の記事に書くとして、今回は、個人的にずっと気になっている長女の癖に関して書いてみようと思います。
左右対称のルール
さて、早速ですがその癖とは、「左右対称のルール」とでも名付けましょうか。
例えば、コップのふちに右手が当たるとします。そうすると、左手も当てないと気が済まない、何なら、手のひら側が当たった場合、今度は甲側も右、左、と当てる。と言った動きです。
テーブルのふちやその他あらゆる物、ぶつかった場所などに発動します。
ちょっと何を言っているのかわからないという人も、わかる~!と思ってくれている人も中にはいるかもしれません。
私がこの行動の理由を詳しく知ったのには、それを説明してくれる人がいたからです。
それは、我が家の発達障害の参考書替わり、ASDタイプ、グレーゾーン(※診断は受けておりません)の ちち です。
なんと、父にも同じルールがあったのです。
彼曰く

バランスがあるじゃない?
なのだそうです。

バランス?あー、わからないでもない。笑
はい、実はこれだけで何となく感覚的にわかる気がしたはは(私) です。が、皆さんはどうなのでしょうか?
ここでのバランスというのはおそらく自分の中で心地よいバランス。左右上下感だったり、テンポだったり、何となく対象が取れるよう感覚的に落ち着くポジションへもって行けるような、体の使い方だったりのことなのだと思います。
具体的な行動例で言うと、偶然手に触れてしまったり体に当たってしまったりしたものに対して左右、時には上下の当たりかた、動きについて自分の落ち着くバランスを取りたいのだそうです。
先述の通り、何となくそういう感覚があっても不思議ではないと思うはは ですが、ただ、この癖の場合、きっと自分ならそれをしている時間のロスの方が気になってしまってストレスになるんだろうな(笑)とも思いました。
こう考えると、この癖の話はそれぞれの心のバランスのとり方があるというだけの話かもしれません。
ですが、始めたので話を戻します。
ここで、参考書代わりのちち に発動する行動例を挙げます。
これも長女の感覚とおおよそ同じだと思いますが、右手をぶつけたら左手も、それが手のひら側なら甲側も、それも、右手のひら、左手のひら、左甲右甲、右甲左甲、左手のひら右手のひら、と左右のバランスを整えながら戻ってくる。のように上下左右などのバランスが整っていとと感じる流れ一連が、きれいに成功した方が気分がいいようです。
ちち とはは は20年ほどの付き合いになりますが、実は、はは 、それらの行動をあまり気にしたことはありませんでした。が、よく考えると目の端で目撃していたような意識もあります。笑
そうなると、はは がすっと理解できたのは、それを見てあらかた想像はしていたということなのかもしれません。
どちらにしても、公にやることはさすがに妙だと本人も感じて、ひっそりとできるように自分の中の許せるゾーンは守りつつ、行動の仕方に気を遣っていたのだなと、びっくりした出来事でした。
癖はストレスのコントロール方法の一つ

このことで思った事は、そうやってストレスのコントロールができればそれに越したことはないよね。ということです。
発達障害ではこだわりが強いことが見られると言いますが、これは次女やちちにも多分に見られます。
はは の印象としては、このこだわりはストレスの反転のようなもので、ストレスが多ければ些細なことが気になって一層そこにこだわってイライラしてしまったりすることが多くなるように思います。
そこで、癖というものがこのイライラを自分の中でのバランスをとることに役立っているのではないかと思います。
長女の癖を知ると、単なる自己防衛反応なのかもしれませんし、発達障害からくるこだわりや、不安を抑える行動なのかもしれません。
何にせよ、ストレス軽減や不安解消のためにやっていることには変わりないと思うので、この癖を目立たない範囲で利用していくことはいいことだと思いました。
癖が自分を映す鏡になるかも?
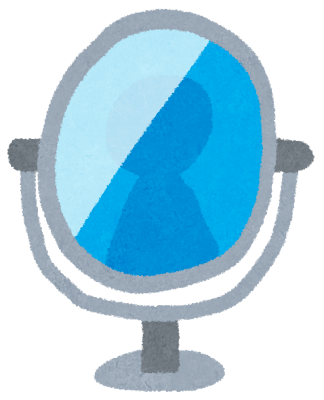
また、ちち の話を聞いてみると、この行動は何となく、ルールの範囲がストレス状況によって拡大する(適用ルールが厳しくなる=落ち着くまでの行動のプロセスが長くなる)ということがあるような気がしています。
これは逆に周囲や本人が、その子、その人の無意識のストレスに気づくきっかけでもあると考えられます。私個人的には、そちらの方向でとらえています。そうすれば自分と向き合う材料が一つ増えるかもしれないと思うからです。
癖に気づいてよかったこと
長女の癖が家族公認になった
そのルールをははが知ったと長女自身が認識した後は、長女の左右対称のルール・癖は、ははの前でも堂々と発動するようになりました。例えば、はは の右手をつかんだら、左手もつかまないといけないというように。はは もはは もわかっているので、笑いながら付き合っています。
なんだか、厳密に言うとつかみ方もバランス加減があるようですが、その辺は はは にはよくわかりません。
それを知ってからは家族も「お、発動してる」と思うようになって、長女も気にせず家族の前ではできるようになって、その行動が受け入れられる場ができたことで癖の出甲斐もあるかなと思っています。笑
外ではおそらく我慢するようにどんどんなっていくでしょうし、今までそうだったように、もう外では気をつかっていると思います。家くらいは気にせずにできる場にしてあげた方が本人のストレス対策にもいいかな?と気づけて良かったと思っています。
ちち との会話のネタが増えた
因みに、 ちち もその感覚を共有できたことで、家では存分に出せるようになったようです。今ではむしろ夫婦間でツッコミを入れたりして、会話の材料になっています。
例えば…
先日、部屋の中で移動中に一瞬華麗なステップを踏み出した ちち。ピンと来たはは は「つまづいたの?笑」
ちち「そうそう、右で躓いたから左でも躓いて~、、、」とにやにやと説明を始めるちち
「笑 (やること増えて)大変やねぇ(冗談)」
といった具合で面白く見ています。
癖は自分の安定剤
人には何かしら癖というものがあると思うのですが、どうでしょうか?
癖がストレスの調整や心を落ち着かせようとするために出ているのならば、妙な癖があるから直すなんて必要はないように思います。(人に迷惑をかけていなければ)
それよりも、自分の感情に気づけるきっかけになればいいなと思います。
と、言うわけで、妙な癖を見ると、「そんなこと、他人が見たら変に思うからやめなさい!!」と言いたくなってしまったり、心配になってしまいますが、自然とそのあたりも自分でコントロール出来るだろう。むしろこちらも癖をヒントにさせてもらおうと思ったはは でした。
今回は長女とちちの癖、マイルールが同じだったことでこれは発達障害の脳タイプに関連してのことなのだろうか?と疑問に思ったので、記事にしてみました。共感いただける方、また、このような不思議な癖を悪いように考えてしまう方の気が少し楽になるような記事になっていたら幸いです。
後日談
長女の癖の話から公認になった、ちち と長女の左右対称のルール。
それもすっかりなじんだ頃、次女が、
「お姉ちゃんがこうやってぇ~、右の手のひらあたったらぁ~、左も当ててってしてたからぁ~、私もした~!」
と言っていました。
え?これ、私以外の3人ともの癖になるんですか!?と、さすがにその光景を想像してちょっと動揺したはは。

!!!?
どうやら、左右対称のルールは次女の癖候補に上ったのでした。



コメント