前回に続いて今回は次女の発達検査と心理検査について書いていこうと思います。
今まで主に次女の話をしてきましたが、具体的な検査結果とその使い方について書いていなかったので、今回は次女の場合についてみていきたいと思います。
長女の時と同じく、二種類の検査をしていて、それぞれ見られること、目的も違いますので、検査については長女の検査について書いた記事と同様の説明を前半に載せておきます。
長女の検査についての記事を読まれた方は、目次より、「検査を踏まえて現状を把握する」まで飛んでからご覧いただけますと幸いです。
ここでは検査とわたしが見ている次女の現状を踏まえた次女の得意不得意を見ていきたいと思います。
個人的には、これらの検査は、客観的に子どもたちの状態を見るためのとてもいい機会になったと思っています。
検査に対して抵抗感のある方のご参考になればと思い、”子どもと向き合う方法の一つとして発達検査というものがある”という目線で、我が家の場合の話を書いています。
発達検査と心理検査について
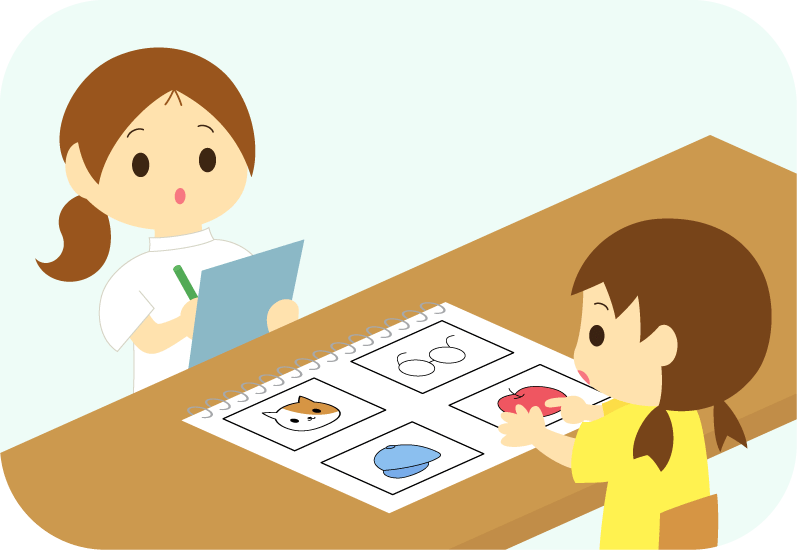
次女がした検査は、発達検査「新版K式発達検査2020」と心理検査「日本番WISC-V」です。
それぞれに受けた機関や読み取れる内容が違うので、まずは私の理解する範囲で、それぞれの検査について簡単に説明しておきます。
発達検査「新版K式発達検査2020」
検査概要
今回次女がした発達検査は、「新版K式発達検査2020」というものです。この検査でみられるものとしては、
・「全体領域」「姿勢・運動領域」「認知・適応領域」「言語・社会領域」の検査課題への子どもの反応から発達の状態を多面的に評価するもの。
各能力が平均値に対してどれくらいの年齢に相当する発達をしているのかがみられる。
それぞれの項目に上限値と下限値がある。
・対象年齢は主に0歳~成人ですが、主に0~7歳未満の子どもに使用される検査のようです。
・検査時間は3~4時間ほど。実際は3時間ほどだったかと思います。
子どもの能力が年齢なりの成長をしているかどうか、それ以上か、ゆっくりかということを相当年齢としてみることができます。
まず初めに、保護者と検査員さんとのお話があります。子どもの幼少期の様子、現在の様子、どういった子か、何に困っているかなどの質問があります。
長女の検査は女性の検査員さんと二人で行われました。
検査結果はあくまでも目安ですが、(そのテストを受けた際のコンディションでも前後はあると担当の方は言っていました。)検査後は子どもの得意な要素、不得意な要素、それによって日常生活にどのような困りごとが起こりそうかを丁寧に説明してくださり、日常の困りごとの原因と対策のヒントが手に入れられたり、親としても認識をしやすくなりました。
そして、私の場合は、検査のおかげで日常の謎が一部解けたことで、怒らなくて済むことが増えました。
参考:新版K式発達検査でわかることは|やり方と結果の見方について解説
検査を受けた施設
地域の子ども相談センター
子ども相談センターは各市町村によって名称が異なるようですが、発達障害に限らず、子どもの発達について相談や検査ができる場所なので、気になる方は一度相談されてもいいと思います。
心理検査「日本版WISC-V」
今回次女がした心理検査は、「日本版WISC-V」というものです。
検査概要
・知的水準の把握
・6歳から16歳11か月までの子どもを対象に設計
・言語理解、流動性推理、空間能力、ワーキングメモリ、処理速度の5つの認知領域を評価する
言語理解…言葉を理解したり、説明する力
流動性推理…非言語情報の特徴を把握し、関係性や規則性などを察する力
視覚空間領域…空間にあるものを正確に把握・認知する力
ワーキングメモリ…耳から聞いた情報や目で見た情報を一時的に記憶しつつ、その情報を使って頭の中で様々な処理をする力
処理速度…目で見た情報を素早く正確に処理して作業する速さ
得意不得意、課題などを明確にするのに役立つ。具体的な強みや支援が必要な領域を特定、それにより教育者や心理学者は個々のニーズに合わせた教育計画や介入策を立てることが可能になり、子どもたち一人ひとり潜在能力を最大限に引き出す支援を行うことができる。
※検査の結果から得られたデータはその人のすべてを表すものではありません。
※指数などの数値は今後成長していく上で変化する可能性があります。
※検査時の状態によって結果の揺らぎはあります。
参考:WISC-V(児童向けウェクスラー式知能検査)とは?わかりやすく解説!
検査を受けた施設
発達検査のできる小児科
心理士による検査
検査をふまえて次女の現状を把握する
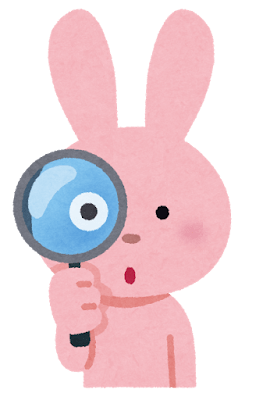
発達検査から見えてきたこと
発達検査の結果
次女が発達検査を受けたのが7歳1か月に対して、結果のc発達年齢は7歳6か月と、年齢相応でした。
次に「姿勢・運動領域」「認知・適応領域」「言語・社会領域」のうち、次女が検査した項目は後の2項目、「認知・適応領域」「言語・社会領域」です。
また、先述の発達検査についての説明で述べたように、各項目に上限の発達年齢と下限の発達年齢が出ます。
これを踏まえて、次女の結果が以下になります。
「認知・適応領域」(周囲の環境の理解や、問題解決に取り組む力を評価する)においては上限が8~9歳、下限が5~6歳
「言語・社会領域」(発語やコミュニケーション能力などの社会性においての発達度合いの参考になるもの)は上限が9~10、下限が7歳程度
全体的に各項目ともそれほど実年齢から離れていないようですが、ばらつきがあり、各項目の中でも得意不得意を持っているということになります。
次女の場合、検査内容から読み取れることは
・耳より目からの情報が理解しやすいかもしれない。
・見て、すぐ動作に移すことの苦手さがある。特に板書など。
・周囲の環境変化を理解して迅速に行動へ移すことが苦手なため、変化(ペース)についていくことの困難さがある。
現状の理解
この検査結果を踏まえて、私が感じる次女の特性をまとめると、
・理解はするが、動作に至るまでの速度にゆっくりさがみられ、学校生活全体の影響につながると思われる。
・発達年齢的には一見してそれほどの差は無いように見えるが、こだわり、認知の特徴が影響して、更に社会領域の把握の苦手さ、コミュニケーションの苦手さにつながると考えられる。
次女の場合は「認知、適応領域」の下限が6歳程度と、当時の年齢7歳とそれほど離れてはいないのですが、現状は動作の反応が出るまでのゆっくりさがかなり目立っていること、それがASDの気質であるこだわりなどの強さ、認知の歪みなどが影響して、さらに苦手さを助長してしまっているのかな?と感じます。
実際、周囲のペースにどんどんとついていけなくなり、本来ならできることも出来なくなってしまいがちな次女には、ASDのできないことへのプレッシャーとこだわりの天秤では、こだわりの方を重視してしまい、周囲のペースにさらに合わせられなくなっているように見えています。
心理検査から見えてきたこと
心理検査の結果
こちらも全体の平均としては年齢相応でした。
検査内容5項目の結果は以下の通りです。
「言語理解」「視空間」に関しては平均~平均の上。
「流動性推理」平均の上~非常に高い。
「ワーキングメモリ」非常に高い~極めて高い。
一方「処理速度」に関しては平均の下から平均。
全体の状態から見ると、「処理速度」だけ大幅に落ちます。
心理士からの説明によると、「処理速度」に関しても、ほぼ平均の範囲内ではあるそうですが、長女同様、領域間で大きなばらつきがあることが次女自身の中での困りごとにつながっていると思われます。
発達障害と診断される人には、この差異が大きい面がみられると聞きます。
この差異によって、生活をする上での本人や周囲の困りごとが多くなったります。
また、発達検査も同じくだったのですが、検査結果には、心理士とのコミュニケーションの様子も踏まえて観察があり、それらも加味されて診断につながるため、結果には試験時の態度、姿勢、反応などの様子も書かれていました。
現状の理解
この結果と、現状私が見る次女の姿を合わせて見えてくることは、
・情報を保持して操作する能力が特に高い。
・聴覚の記憶より視覚情報の記憶と処理が非常に得意。
・抽象的な理解は平均以上の能力は持っているが、より語彙の理解の方が得意。
・処理速度に関して、数値は平均だが、次女の中ではとてもゆっくりさが目立っていて、現状は生活ペースに大きく影響がでるほど足を引っ張ってしまう状態になっている。具体的にはテストが時間内に終えられない。板書が時間内に終えられない。周囲のペース(行動)についていけないなど。学校生活では特に、先述の時間があれば発揮できる能力を生かせる場面がかなり少なくなってしまっている。
・量的推理と言った抽象的な概念の理解や法則の理解など情報から意図や概念を読み解き、推理、応答する能力が高いので、じっくりと考えられることで力を発揮し、問題解決に行きつくことができる。
また、環境と次女自身のメンタル循環に余裕があれば、その理解を即座に会話に反映することも可能。
・行動を迅速にこなすことの苦手さ、特に書字の運動速度にゆっくりさが目立つ。かかれている情報の認識、記憶、理解はできるが、書く作業を伴うことにより、作業がゆっくりになりやすい。
・意思決定などの判断を下すことに時間がかかりやすいため、行動がワンテンポ遅れがちになってしまうことで授業や会話など周囲とペースが合わないと出遅れてしまいやすい。
と言ったところでしょうか。
一見して得意なことが多いようですが、これらがASDの気質により、より苦手を助長させていると考えています
次女の場合は、抽象的な理解は平均以上の能力は持っているが、より語彙の理解の方が得意なので、語彙に注目がいきやすくなります。そこに、ASDのこだわりの発動によってより抽象的な理解力は発揮されにくいように思いますし、ASDによる感覚過敏や不注意、不安によって判断を下すことを躊躇してしまうということが日常的に起こっているのではないかと感じました。
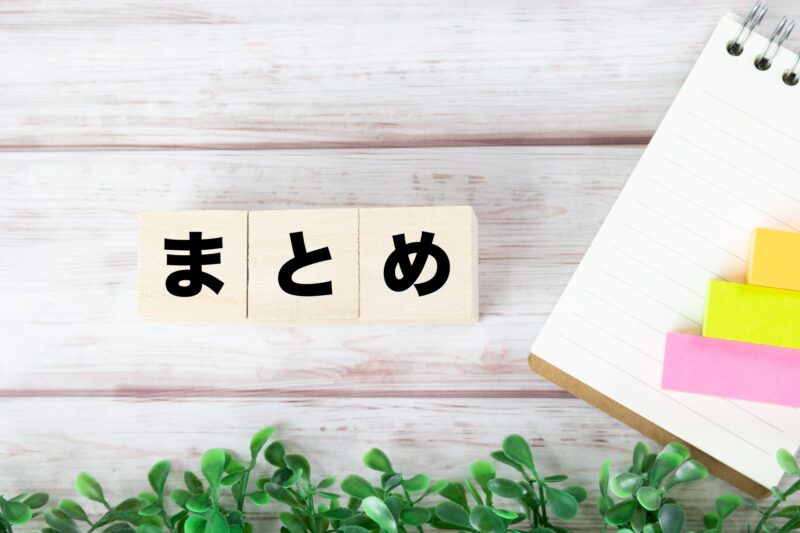
まとめ
いかがでしたでしょうか?
我が家の場合は発達検査と心理検査からこんな感じで現状と重なる部分や、それがどういった要素から来ているのかを考えたり、そこからアプローチ方法を考えるということにとても役立つと思いました。
大切な子どもの困りごとに気づけるきっかけになる、自身の子どもに対する声掛けのヒントになると私は感じます。
わが子に対してどうしてそういった反応になるのか困っている方たちの参考になればうれしいです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓





コメント