「日常ー学び」では発達障害を持つ我が家の姉妹のエピソードや、そこから学ぶことと、ちょっとクスっと笑える日常の会話など、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
整理整頓が苦手な長女
先日、次女に続いてASDと診断を受けた長女。
そんな長女は整理整頓、片づけがとてもとても苦手です。
そして、荷造りや日常の学校の準備など、持ち物をそろえることも苦手です。
我が家の姉妹は超絶マイペースなので、二人とも、毎度「はい、用意するよ!」と一緒にできるように促すことが必要ですが、特に長女に関しては生活に必要なことの大半には興味がない様子で、結局、持ち物を用意することも、自分でできるようになりたいと思ってくれないまま小学校に入学しました。
とはいえ、まだ小学生になったころなんてそんなものだと思います。

よし、小学生になったし、これから準備や整理整頓も少しずつできるようになるだろう!!私もサポート頑張ろう!
とわが子の成長を期待したはは(私/はゆまーま)です。
当時はまだ発達障害がどんなものかも知らない、発達障害というワードも意識していないときでした。

ところがそんなははの思いをよそに、1年生、2年生、3年生とどれだけ学年が進んでも”明日のランドセルの用意”をすることは彼女の意識には定着せず、「明日の用意した?」は、毎日何回も何回も言うセリフの一つになってしまいました。
それどころか、4、5年と学年が上がるにつれ、全く用意をする姿を見ることがなくなりました。さらに、手紙も連絡帳も何回言っても出てこない。
私がランドセルから手紙と連絡帳を引っ張り出すことは簡単ですが、長女にはそれが逆効果に働き、反発とさらにやる気を奪う行為だとわかったこと、とにかく自分でできるという思いを優先させたい思いもあり、それはしないようにしています。そうすると、結果どうなるかというと…?
一日の最後には、寝る準備の声掛けにいそいそして、手紙や連絡帳を終ぞ確認できていないことを忘れ、翌日に、「昨日、手紙確認し忘れた!」とか、「連絡帳にサインするの忘れた!」
そんなことになりがちでした。
わかっているけどできない
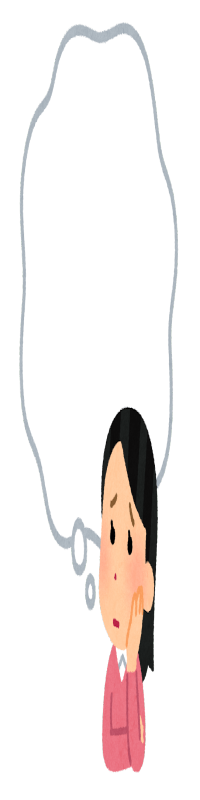
長女は小学生になっても相変わらず”用意に気が向かない”状態でしたが、最初の頃は声をかけるととりあえずやるといった状態ではあったので、学校の準備もそのうちに日常になっていくだろうと思っていました。
が、先述の通り、学年が上がるにつれて、次第に時間割の確認をしている長女の姿を見なくなり、いつの間にかすっかりランドセルの用意をしている姿を見ることがなくなってしまいました。

明日のランドセルの用意はしたの?

うん!

いやいや、今ずっと同じ部屋にいたけど、帰ってきてランドセル放置したまま用意する姿見てないよ?
と言う感じ。
なんだかとりあえず「うん」という癖がついてしまっている…。
ははとしても散々、「なぜやらないと自分が困ることなのにしようとしない!?」と、あれやこれやと格闘してきた中で、結局自分で必要だと思ってもらうことしか打開策はないのでは?という結論に、今のところなっています。
ということで、あれやこれやと自発性を促すことに力を費やしながら、直接手を出すことは極力控えています。忍耐以外の何者でもありませんが…。

困ったらするようになる…。困ったらするようになる…。困ったら…。(呪文のように言い聞かせる)
ははから見た長女の現状としては、必要なことはわかっているのに、”今は面倒くさい”や”目の前の楽しいものが優先”になり、そのコントロールがどうしても自分でできない状態なのではないかと感じています。
つまり、長女自身もわかっているけど、なぜかどうしてもできない。
長女の強い拒絶
長女が機嫌よく、自分でできる!という自信をもって生活が回るように促す。というスタイルをできるだけ取りたいと思っているははですが、それには理由があります。
長女は、突然強い拒絶に入ることがあるのです。
長女自身、わかっているのにできないことに加えて、この拒絶モードに入ると余計に物事が進みません。
特に学校関連の物の管理についてはこの拒絶モードは全開になります。
小学生になっていつからか、長女は親や祖母がランドセルや筆箱などを開けようとすると、強固に拒絶するようになりました。
ランドセルや筆箱の中は、どうしたらそんなにぐしゃぐしゃになるのだろうという状態で、見かねて言ってみていた頃もありましたが、
「このプリントはもっていかなくていいんじゃない?」断固拒否。
「一回全部出してプリントとそうでないもの分けよう!」断固拒否。
ランドセルを開けようとすると、力づくでランドセルを開けさせまいと激怒したことも何度かあります。
最初にランドセルに触れようとすることに敏感だなと思ったのは低学年か、3年生あたりでしょうか?
ある日、永遠に出されない連絡帳と手紙に業を煮やしてランドセルに手を伸ばしました。
そうすると長女はとても強い拒絶を見せました。
これは、ははの勝手な予想ですが、その時、長女自身もランドセルの管理ができていないことはわかっていたのではないでしょうか。自分でもぐしゃぐしゃだとわかっているから見られたくないと思ったのだと思いました。
こうなると一方的にこちらの目的を果たそうとしようものなら、とんでもない激怒を見せることは予想できます。
そんなわけで勝手にランドセルを開けたりせずに、

今日は忘れ物とかなかった?
学校で困ることなかった?
くらいに、遠回りに確認する程度でいるのですが、聞くと大抵

うん!!
という長女。けれど、いざ連絡帳を見ると、今日の忘れ物欄に記入があったり…。
「たぶん、今日忘れ物があった事も今は忘れているんだろうな。」と思うはは。
(この困った状態の対処に、今は一番頭を悩ませているところですが、私としては、このイライラについて考えることが長女の今後の社会的な課題に向き合うことにもつながるのではないかと思っています。)
※長女のイライラと対処について書いた記事はコチラ↓
長女なりの工夫
さて、こんな感じで、直接どうにもできないややこしい状態の長女ですが、すっかりランドセルの準備をしなくなったのは4年生ごろだったでしょうか?

最近ランドセルの用意してないけど、大丈夫なの?

学校においてきているから大丈夫

あれ?置き勉禁止じゃないの?
物の管理が苦手で忘れ物も多くなりがちな長女なりに、自分で必要なことだと思ったのかもしれない。これも、長女なりの工夫か。と考えて見て見ぬふりをしていました。
そうするうちに今度はランドセルにプリントやらなにやら雑多に詰め込まれている様子が顕著になってきました。
「それは連絡袋にいれたら?」
「一度プリント全部ランドセルから出してみたら?」と声をかけると長女はやっぱり断固拒否の姿勢を取り始めます。
整理することは断固拒否、私が手を出すと激怒、本人の負荷が増えると日常が余計に回らず、長女のストレス値は無限に上がる。
そんな感じなので、本人がなんとか学校生活をできているうちはそのままにしておこうと思っていました。
が、ある日のこと、長女のランドセルを持ち上げる機会があり、驚きました。

重っ!?
小学生のカバンとは思えないくらい激重なランドセルにびっくり!さらに、見た目にもパンパンに膨らんでいるではありませんか!
雑多に詰め込まれた片づけられない人の見本のようなランドセルだという認識はあったのですが、ここまでパンパンに膨れ上がっているとは!!
工夫 = 困りごと
長女はかなり小柄なのですが、自分とそれほど変わらないのではないか?と思うほどの激重ランドセルを毎日背負って登下校していることに気づいたはは。これは非常事態!と、さすがにランドセルの中を確認しました。
そこには歴代のプリントが、教科書やノートの間に挟まって、必要な教科書がどこなのか、そもそも教科書も入っているか、ぱっと見たところでは判断ができないほどに、ぎっしりと詰め込まれていました。

えええ!!!?
このころには宿題プリントや手紙を見失うことは当たり前、やった宿題を持って行き忘れる。教科書を忘れる。など問題が顕著になってきていた長女。
ならばいっそ、すべてを持ち帰り、そのまま持っていけば忘れ物は解決する!!おそらく長女はそう考えたのでしょうが、その長女なりの工夫は現状をどんどん悪化させていっているようでした。
ここまでくるともう、確実に長女にとっても自分では解決できない困りごとだ!!そう思いました。
きっかけは学校での整理整頓
毎年、長期休み前は次女も巻き込んでランドセル入れとランドセルを整理する機会は設けるようにして、この時ばかりはランドセルからすべて出して、プリントとそうでないものを分けてと一つずつ整理の仕方を教えます。
が、普段はそれを受け入れたがらない長女。
因みに、発達障害の子は口頭での話よりも可視化した方が理解しやすいと言われますが、我が家も貼りだせるような札を作ったり、できた!を見える可するシール制度にしたり、一緒に計画を立てたりして可視化できる表にして貼り出したリしましたが、その可視化されたものの存在を忘れて、なかったことになり、無に帰します。
正直家では限界を感じていました。
そんなこともあっての5年生。
担任の先生に、少しずつ長女の困ったところをサポートしてもらって、外で”できる”を学んでもらうようにした方がいいと思うようになりました。
そうやって担任の先生に少しずつサポートの必要性を訴えているとき、先生が長女のお道具箱の中身の大変さに気づいてくれるということがありました。
夏休み前、長女が宿題プリントを忘れ、学校に取りに戻ったことがきっかけで、先生がお道具箱の中を確認することになり、あまりの状態に、先生が一緒にお道具箱の中身を整理してくれたことがあったのです。
そこで、すっきりとしたお道具箱に喜びを覚え、自分もできる体験を積めた長女は自信をつけたようで、家でも2,3度、スイッチが入るということが起こりました。
家でも自らランドセルの中身とランドセル入れを整理し始めたということがあったんです。
長女も外ではある程度やる気スイッチが入っている状態ですし、家族以外には怒りません。だから、”できる”体験が功を奏したんだなと思いました。そして、療育というものの家庭での限界と外からのサポートの必要性に確信を持つきっかけになりました。
ヒント💡 整理整頓 ”物の住所を決める”ことの大切さ

片づけのコツとして”ものの住所を決める”というのを聞いたことはありますか?このことの大切さを実感するできごとがありました。
担任の先生のおかげで整理整頓ができたという体験を嬉しく受け止めることができた長女は、夏休みに入って間もなく、片づけスイッチが入った時がありました。
いままで、家で積極的に片づけをしている姿を見たことは、私の記憶している範囲ではなかったように思うのですが、その時の長女は違いました。
基本的には床に広がっていたものを机の上に積むという片づけだったのですが、長女は、その中でも、定位置を作っている物はしっかりとその場所へ持って行っていたのです。
私はそんな長女を見て、定位置が決まっているもののところへまとめることはできるのだな。と感動しました。
実は、私自身、片づけが得意ではないのですが、片づけが身につかない子どもたちに悩むなかで、定位置を作って少しでも片づけが身についてくれないだろうか、と、長年、少しずつ物の住所決めに取り組んできました。
何年も持ってきてそのまま散らかすという状態しか見てこなかっただけに、やっと効果が発揮されて、とても嬉しかったです。これはやってよかったと思った出来事でした。
また、今回のことで整理整頓の課題も見えてきました。
長女の整理整頓の課題としては、大枠の場所に置くことはできても、例えばノートを崩れないようにそろえたり、重ねたりすることや、おもちゃをケースが閉まるように入れる、など、各スペースを整頓することはかなり難しいようです。
物を最低限にして、見える収納で定位置を決めるなどの本人にあった工夫ができれば、さらに整理整頓はできるようになるのでは?と希望を感じました。
まとめ
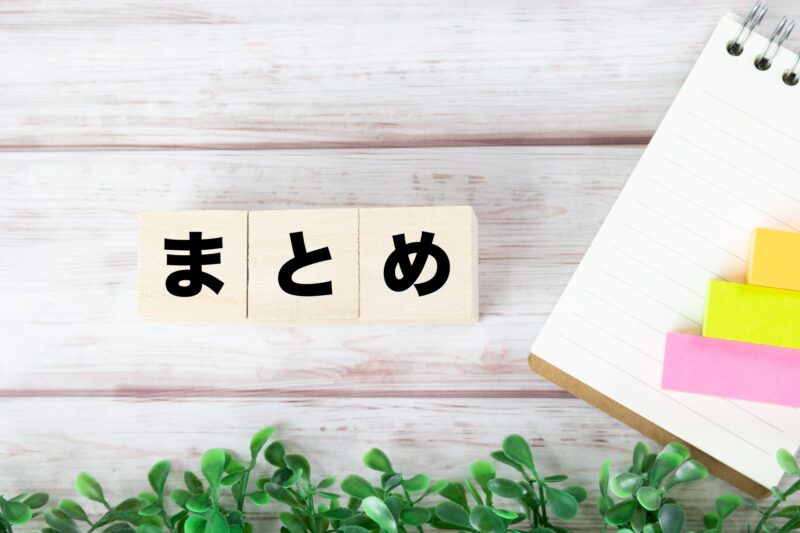
今回は長女の激重ランドセルから療育のアプローチや整理整頓できる環境のアプローチのヒントを少し掴んできたかなと思った話を書いてきました。
整理整頓が得意な人なんてあまりいないかと思いますが、発達が関係しているのではないかと思う極端な整理整頓の苦手さのエピソードを通して、それが本人の困りごとにつながること、さらに、できないという自身の無さ、うしろめたさがその子の負の連鎖になるのではないかということをこのエピソードから感じ取っていただければ、療育のアプローチ方法のヒントになるのではないかと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓






コメント