小学5年生になる長女も先日、次女と同様にASD(自閉スペクトラム症)の診断がおりました。
それまでに、二種類の検査をしました。それぞれ別ルートの検査で、目的も違うものですが、
個人的には、これらの検査は客観的に子どもたちの状態を見るためのとてもいい機会になったと思っているので、今回はその発達検査について書いていこうと思います。
長女が受けたのは発達検査と心理検査です。
ここでは検査と現状を踏まえて見えた長女の得意不得意を見ていきたいと思います。
検査に対して抵抗感のある方のご参考になればと思い、子どもと向き合う方法の一つとして発達検査というものがあるという目線で、我が家の場合の話を書いています。
発達検査と心理検査について
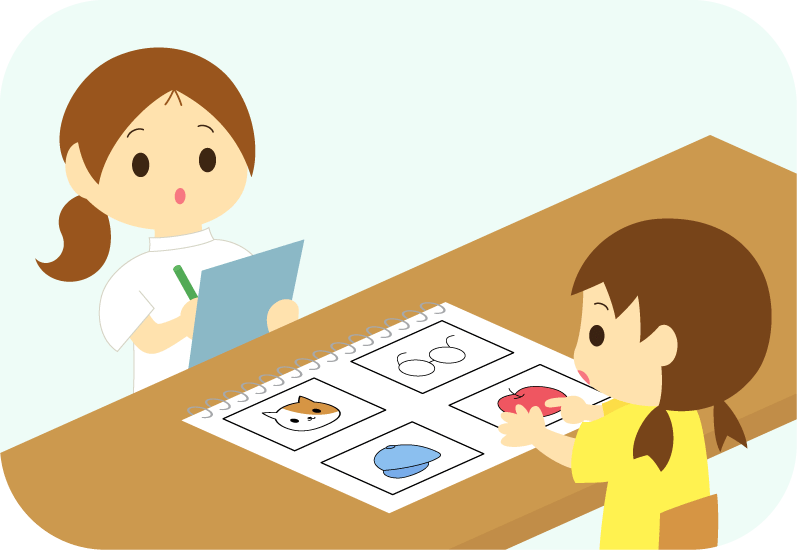
長女がした検査は、発達検査「新版K式発達検査2020」と心理検査「日本番WISC-V」です。
それぞれに受けた機関や読み取れる内容が違うので、まずは私の理解する範囲で、それぞれの検査について簡単に説明しておきます。
発達検査「新版K式発達検査2020」
検査概要
今回長女がした発達検査は、「新版K式発達検査2020」というものです。
・「全体領域」「姿勢・運動領域」「認知・適応領域」「言語・社会領域」の検査課題への子どもの反応から発達の状態を多面的に評価するもの。
各能力が平均値に対してどれくらいの年齢に相当する発達をしているのかがみられる。
それぞれの項目に上限値と下限値がある。
・対象年齢は主に0歳~成人ですが、主に0~7歳未満の子どもに使用される検査のようです。
・検査時間は3~4時間ほど。実際は3時間ほどだったかと思います。
子どもの能力が年齢なりの成長をしているかどうか、それ以上か、ゆっくりかということを相当年齢としてみることができます。
まず初めに、保護者と検査員さんとのお話があります。子どもの幼少期の様子、現在の様子、どういった子か、何に困っているかなどの質問があります。
長女の検査は女性の検査員さんと二人で行われました。
検査結果はあくまでも目安ですが、(そのテストを受けた際のコンディションでも前後はあると担当の方は言っていました。)検査後は子どもの得意な要素、不得意な要素、それによって日常生活にどのような困りごとが起こりそうかを丁寧に説明してくださり、日常の困りごとの原因と対策のヒントが手に入れられたり、親としても子どもの性質を認識をしやすくなりました。
私の場合は、検査のおかげで日常の謎が一部解けたことで、怒らなくて済むことが増えました。
参考:新版K式発達検査でわかることは|やり方と結果の見方について解説
検査を受けた施設
地域の子ども相談センター
子ども相談センターは各市町村によって名称が異なるようですが、発達障害に限らず、子どもの発達について相談や検査ができる場所なので、気になる方は一度相談されてもいいと思います。
心理検査「日本版WISC-V」
検査概要
今回長女がした心理検査は、「日本版WISC-V」というものです。
・知的水準の把握
・6歳から16歳11か月までの子どもを対象に設計
・言語理解、流動性推理、空間能力、ワーキングメモリ、処理速度の5つの認知領域を評価する
言語理解…言葉を理解したり、説明する力
流動性推理…非言語情報の特徴を把握し、関係性や規則性などを察する力
視覚空間領域…空間にあるものを正確に把握・認知する力
ワーキングメモリ…耳から聞いた情報や目で見た情報を一時的に記憶しつつ、その情報を使って頭の中で様々な処理をする力
処理速度…目で見た情報を素早く正確に処理して作業する速さ
得意不得意、課題などを明確にするのに役立つ。具体的な強みや支援が必要な領域を特定、それにより教育者や心理学者は個々のニーズに合わせた教育計画や介入策を立てることが可能になり、子どもたち一人ひとり潜在能力を最大限に引き出す支援を行うことができる。
※検査の結果から得られたデータはその人のすべてを表すものではありません。
※指数などの数値は今後成長していく上で変化する可能性があります。
※検査時の状態によって結果の揺らぎはあります。
参考:WISC-V(児童向けウェクスラー式知能検査)とは?わかりやすく解説!
検査を受けた施設
発達検査のできる小児科
心理士による検査
検査をふまえて現状を把握する
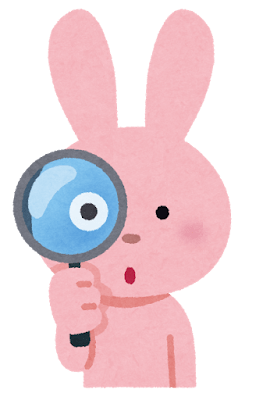
発達検査から見えてきたこと
発達検査の結果
長女は発達検査を受けたのが10歳1か月に対して結果発達年齢は10歳7か月と年齢相応でした。
次に「姿勢・運動領域」「認知・適応領域」「言語・社会領域」のうち、長女が検査した項目は後の2項目、「認知・適応領域」「言語・社会領域」だったのですが、それぞれ上限の発達年齢と下限の発達年齢が出され、長女はこの2項目のうち「言語・社会領域」の検査の上限が成人、下限が7、8歳程度でした。
「言語・社会領域」は発語やコミュニケーション能力などの社会性においての発達度合いの参考になるもののようです。
長女の場合の検査内容から読み取れることは以下の通りです。
・数を復唱するなどの耳から聞いた情報をそのまま受け取ることが得意。
・文章の並び替えなどの言葉の差異など、コミュニケーション能力に影響する場面において苦手さがある。
現状の理解
この検査結果の範囲内で実際、私が感じる長女の特性をまとめると、
言語理解、自分の気持ちの表現などの言語表現、社会性、対人関係、言語コミュニケーション能力、社会的ルール、マナーの理解が苦手。
という特徴があると思います。
ここから、さらに、現状の分析をすると、例えば、私から見る長女は次女と同等の精神年齢のように感じています。
つまり、2歳ほど下のイメージということなのですが、これが「言語・社会領域」での下限7歳~8歳程度という結果とつながっているのではないかと納得しました。
日常でも、コミュニケーションや会話の理解が少し追いついていないような感覚を受けていて、普段見る長女が、この「言語・社会領域」に大きく影響を受ける部分だからそう感じるのではないかと思いました。
また、この辺りの成長がゆっくりなのに、おかれている環境や周囲の子どもたちの理解レベルが当然小学5年生レベルであることが、長女にとっては、何となく感じ取る自分とのギャップや何者かわからない不安になり、日常の不安やストレス、もやもやにつながっている可能性もあるかなと感じます。
一方で、同じ「言語・社会領域」の中でも成人レベルの部分があったように、長女は聞いたことをそのまま記憶することがとても得意です。ぼーっとしているようできっちりと耳からは情報が入ってくるようで、暗記が関係してくる授業などはすぐに記憶できることが多いようです。
心理検査から見えてきたこと
心理検査の結果
次に心理検査の結果としてはこちらも全体の平均としては年齢相応でした。
検査結果から読み取れる内容は以下の通りです。
「言語理解」「視空間」「流動性推理」に関してはすべて平均~平均の上に位置していました。
「ワーキングメモリ」非常に高い~極めて高いの位置に属していました。
一方「処理速度」に関しては平均の下から平均。
心理士からの説明によると、「処理速度」に関しても、ほぼ平均の範囲内ではあるそうですが、問題はこの全項目の上限と下限の差異です。
発達障害と診断される人には、この差異が大きい面がみられると聞きます。
この差異によって、生活をする上での本人や周囲の困りごとが多く、問題の複雑化に関係してきます。
また、発達検査後に受けたお話でも同じくだったのですが、検査の内容には、心理士とのコミュニケーションの点も踏まえて観察があるようで、結果には試験時の態度、姿勢などの様子も書かれていました。
現状の理解
この結果と現状私が見る長女の姿を合わせて見えてくることは、
・視覚、聴覚問わず、記憶力が非常に高い。
・すべきことや意識を向けることが明確であること、かつ、それが興味を持てる対象であることに、非常に高い集中力を発揮できる。
・時間があれば情報を組み立てながら課題に対応する力がある。
・経験を生かすことは得意。
・処理速度のゆっくりさが目立っていて、数値的には平均だが、現状はかなり足を引っ張ってしまう状態になっている。具体的にはテストが時間内に終わらせられない。周囲のペース(行動、会話、その他コミュニケーション)についていけないなど、先述の時間があれば発揮できる能力を生かせる場面がかなり少なくなってしまっている。
・複数の情報から必要な情報を見つけ出すことが苦手なため、白紙の状態から組み立てることが必要な物事に対しては著しくパフォーマンスが低下することがある。
・わからないことは止まって時間だけが過ぎてしまうことがあるので、適切な声掛けが必要。
と言ったところでしょうか。
個人的には最後から2つ目の”複数の情報から必要な情報を見つけ出す”という部分において、日常生活にはこの作業がとても多いために、生活習慣が身につかなかったり整理整頓ができないなどの状態につながるのかもしれないと思っています。
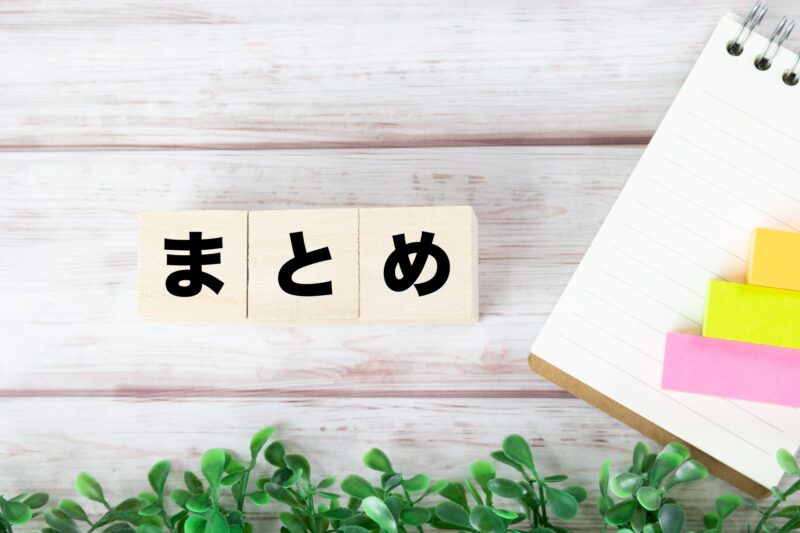
まとめ
いかがでしたでしょうか?
我が家の場合は発達検査と心理検査からこんな感じで現状と重なる部分や、それがどういった要素から来ているのかを考えたり、そこからアプローチ方法を考えるということにとても役立つと思いました。
大切な子どもの困りごとに気づけるきっかけになる、自身の子どもに対する声掛けのヒントになると私は感じます。
わが子に対してどうしてそういった反応になるのか困っている方たちの参考になればうれしいです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓






コメント