我が家のちちは人の顔をあまり認識していないようだというお話を以前に書いたのですが、今回は仕事上でそれがどういった形で表れて困りごとにつながるのか、実例を交えて具体的な様子を書いてみようと思います。
脳内ヒントでは、ASD傾向のある我が家の ちち(※診断は受けていません。)の話をヒントに、大人の発達障害や子どもたちの見ている世界のヒントを得たいという意図で、夫婦での対話形式でお話をしていくコーナーです。
このお話で分かること
職場に2種類の人が3人ずついるという話
似た3人
我が家のちちは人の顔を見ません。理由は情報過多による脳の混乱を防ぐこと、そして、どのみちそれほど違いを認識できないから。
そんなちちが、職場の人と名前を一致させていく方法とは?

最近、職場に似た人が複数いることに気づいたんだよ

笑 何それ?

それがさ、そもそも顔を見ないから気づいてなかったんだけど、どうやら2種類の人間が3人ずつくらいいるっぽい。

笑 得意のジャンルに分けられてしまっているわけね?もう、自動振り分けやな。

んー、で、最近、そのうちの1種類の人たちがわかってきたのよ。

おお~!

最初はさぁ、みんな同じ人だと思ってたんだけど、
最初にミズハラさん(仮名)って人がいて、で、その人と何度か仕事をしているうちに、同じ人だと思っていた人がどうも違う名字で呼ばれていることに気づいたわけ。で、周囲の話を聞いていると、イリエ(仮名)さんが現れたわけ。
で、似た人が二人いるみたいだから、経験上、不用意に名字を呼ばない方がいいなと思って気を付けていたら、カワエ(仮名)さんが出てきたのよ。

笑 みんな水系 笑 そこもややこしいね。

うん、それはいいんだけど。

そこはいいんかい!笑

笑
いや、名字は名字で覚えてるんだけど、どうもその三人が似ているようで、自分が識別できてないらしいとは気づいたんだけど、誰が誰かわからないから、結局不用意に呼べないよね~。

確かに。それは大変だね。
それにしても、改めて聞くけど、そんなにパーツの違いって分からないものなの?

うーん。もはやずっと、顔なんか見てもわからないって思っていることもあるんだろうね。
人の顔にはフィルターがかかる癖があるというか、意識せずにそうなってしまってるから、違いが判らないのかって聞かれてもわからないよね。

もはや長年の工夫が、事実か思い込みも混ざっているのか、かどちらかわからなくさせてるわけだ。

そもそも人を判断するのに、顔を見ると情報が多くて混乱するから、もうずっと人の顔なんて見ないで生活してきてるのよ。そういう風な頭になってるからね。

なるほど、長年の経験上、自分が困らない方法をとってきたから、顔を識別するということを自ら拒絶するようになってしまっているところもあるかもしれないってことか。

そうそう。

あ!なんか、ASDの人で、持ってるカバンで人を判断してるって話聞いたことあるよ?
だから、カバンがいつものと変わったらわからなかったんだって。

そうそう、自分の場合はその人の雰囲気とか、体型、髪型とかで判断してるかな。

でも、今回、ここで問題なのが、その三人の人、みんな同年代の女性で、同じような雰囲気で同じよう体型をしてるんだよ。で、みんな制服じゃない?

あらあら!そりゃあ大変だ!

そうなんだよねー。

因みに、もう一種類の人たちは?

あー、もう一種類はね、2人かな?大東(仮名)さんと東中(仮名)さんかな。

笑! また!? 今度は東系やん! 笑

まぁ、その人たちはあまりかかわらないからいいんだけど。

あ、そうなんだ…。
「人の顔を認識することが苦手」と「大人の発達障害の困りごと」について
今回の ちち の話から、ASDの特性による認識とストレスの悪循環が、大人の発達障害の困りごとにつながるということが考えられると思いました。そして、次の1から5のように悪循環をたどることで社会での困りごとが起きるのではないかなと感じました。
1.そもそも顔の認識が苦手
・興味のあるものにしか注意を向けられない=人への興味がないと注目できないが、人と物が混在して情報としてはいってくるASDには人に注目することが難しい。
・人の表情は非常に変化する物なので、その変化にASDの人は情報過多になり、その人の顔を一つの情報として受け取ることが難しくなる。そして、細部や他情報が入ってくる。パーツの動きやしぐさ、服装、髪型、背景の景色、情景など、様々な情報が入ってきて話が聞けない。
⇓
2.情報のシャットアウト
・情報過多のストレス、話が聞けないことの困り感によって、きちんと話を聞くために、余計な情報をシャットアウトしようとするようになる。
⇓
3.人から顔や目線をそらすことが癖として定着する
・周囲がコミュニケーションの取りづらさを感じる
・ますます人の情報をシャットアウトしてしまうようになり、いざ覚える必要がある時に、特定の名前とその人が一致し辛くなる。
⇓
4.できないことを強く意識、違った学習を重ねてしまう。
・不安感の強いASDの気質によって、人の顔がわからないことをより大きな失敗経験として蓄積しやすく、人とコミュニケーションをとることにマイナスなイメージをため込んでしまう。
⇓
5.社会での生きづらさにつながる
・不安感とストレスはどうせやっても無駄という意識に変化し、それを避け、どうしてもできない自分を責めながら、認知の歪みをさらに強め、周囲への不満につながり、また選択しないという悪循環になってしまうことも十分あり得ると感じました。
種族間の距離による識別のしにくさがあるのかも?

あと、最近思うのは、人間が動物の顔を見分けることって難しいじゃない?
それから考えるに、生物学上遠いものから識別しにくいと考えるとすると、
今回は、その似ている3人と自分は性別が違うのよ。だから余計に識別し辛いのかな?と。

なるほど、日本人からしたら、外国人の顔の見分けとかも難しかったりするもんね。
国が同じでも男女でまた生物学上の距離はあるしね。

そうそう。

そういえば、テレビを見てて、女性の俳優さんはよく間違えるけど、男性の俳優さんは割と見分けられてるよね。それも関係してるのかもね?

そういえば、そうかも。
多人種効果
このことについて調べてみると、「多人種効果」という言葉をみつけました。
「多人種効果」とは、人が自分と異なる人種の人々の顔を識別する能力が、同じ人種の人々の顔を識別する能力よりも劣る現象を指すそうです。心理学の分野では、この現象は「他人種効果」や「異人種効果」とも呼ばれます。
参考:外国人の顔が覚えられない…!その原因は「脳の仕組み」にありました。
ヒント💡相互理解と大人の発達障害に向き合うためのヒント
※ここでの相互理解とは、発達障害を持つ人と、そうでない人との相互理解です。
ヒント1💡
ASDの人が苦手になりやすい「人の顔の認識」我が家のちちの場合は、
髪型で判断。
全体のフォルムで判断。
雰囲気で判断。
その他、いつも固定化されている要素で判断。など
をしているそうです。が、今回のようにこれだけでは判断ができないときもあります。
そんな時は「不用意に名前を呼ばずにコミュニケーションをとる」が、彼の中で一番の方法。
ここで相手はコミュニケーションに少しぎこちなさを感じるかもしれませんが、それは相手に対して失礼のないように最大限配慮した結果である。ということを知っていただけたらいいなと思います。
ヒント2💡
ASD脳の特性上、不安感などからできない意識を強めた結果、意識して人の顔をますます認識することを避ける傾向になっている場合もあるのかも?
ASDの人は、懸命に生きてきて学習した結果、人の顔を見ないようにしているのだなと感じます。
これについてコミュニケーションの違和感を考えるなら、やはり特性の自覚が必要かと思います。
ちち は、最近は、話しながらせめて顔付近をちらっとでも見るということを意識しているようです。
自分の特性を知ることで、自分なりの方法を見つけることができるかもしれません。
とはいえ、常にするにはあまりに神経を遣うことだと思いますので、対する側も、発達、定型かかわらず、顔を見ることが苦手な人なんだな~。くらいの意識を持つことも大切だと思います。
ヒント3💡
最後の多人種効果の話では、そもそも誰でも多人種効果が働くなら、自分と最も近しい種族の顔の認識の練習からはじめてみることも可能性の一つかも?と思いました。
それでできなくても、何事についても、自分と言う人間を大切に扱って、自分の現実を理解してあげようと思う心が少しでも大きくなればいいなと思います。
いかがでしたでしょうか?
あなたは人の顔を見分けることはできますか?それとも苦手でしょうか?
少しでも多くの発達障害を持つ人と社会の相互理解を願います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓
注記:
ちち(夫) は発達検査は受けておりませんが、次女のASDの診断前問診で、次女よりもその項目に共感することが多くありました。私もちち と次女はとても似ていると感じています。
ちち はASDのことを知り、その特徴やそれゆえの苦手分野を知ることで、これまで自分を必要以上に責めていたことに気づき、少し生きやすくなったと言います。
最も、これまでに自分の苦手に気づき、対処法をルーティーン化していくことで対策してきたというちち ですが、その工夫の仕方を知ることでまだまだ考えていけそうなことはありそうです。
※このブログは発達障害のある家族を見るはは(私/はゆまーま)の目線から感じることを書いているものです。専門性のあるものではありません。あくまで発達障害の子どもたちを見る母個人の一意見としてとらえていただけると幸いです。
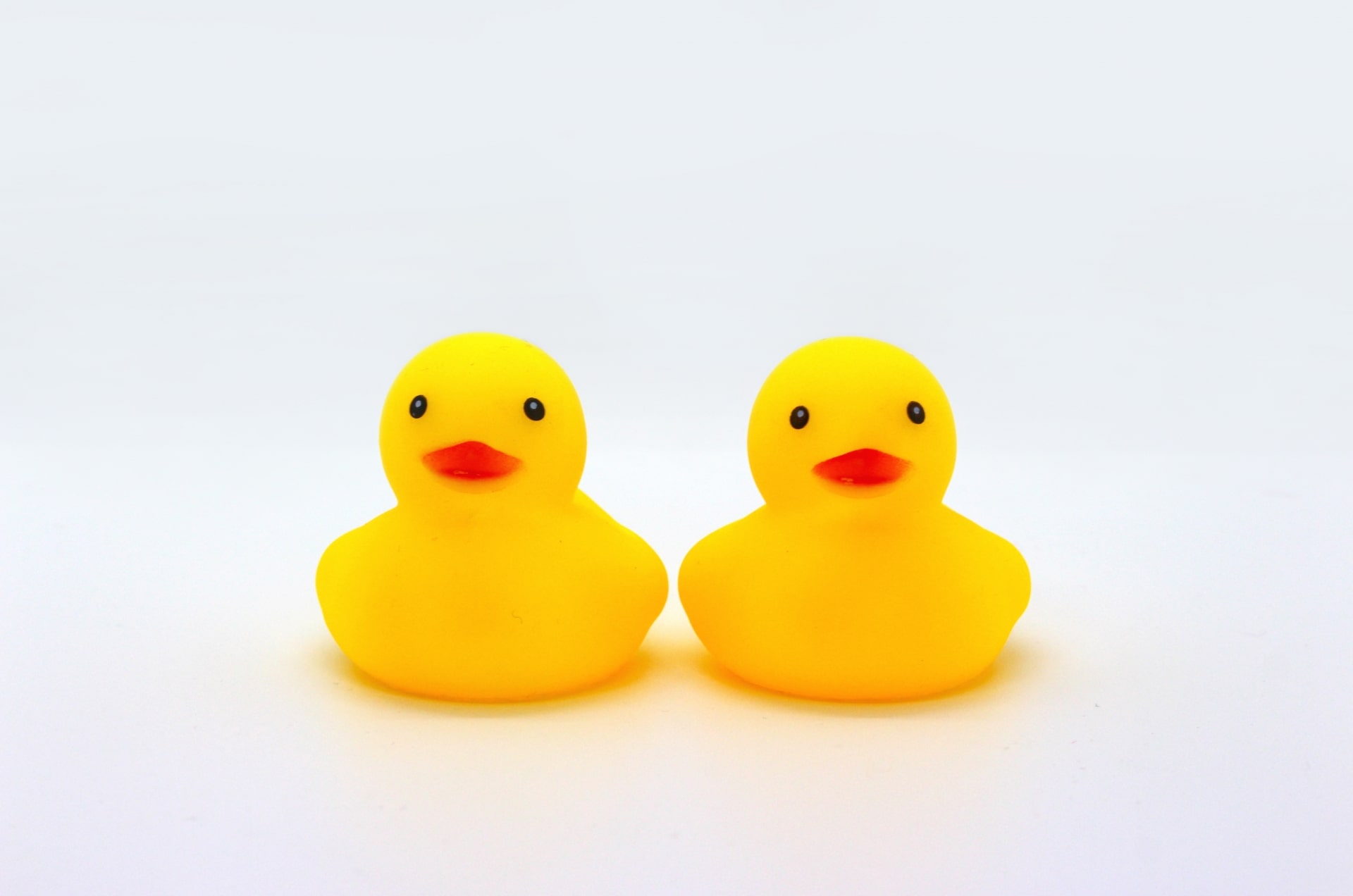


コメント