「日常ー学び」では発達障害を持つ我が家の姉妹のエピソードや、そこから学ぶことと、ちょっとクスっと笑える日常の会話など、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
ASD次女のフラッシュバック!?
突然、なんの脈絡もなく「姉が通知表を勝手に見るから嫌だ」と言い出す次女
ある日の次女。
その日はもうお風呂に入って、後は寝るだけという状態でした。
服を着ながら次女はいきなり「通知表を見たらだめ!!」と怒り出しました。

通知表を見たらだめ!!
誰も通知表を触ってもいなければ、どこへ置いているかを探したくらいでした。
確かに長期休みで通知表は家にありましたが、その時は誰も通知表を手に取っていませんし、話もしていません。
不思議に思っていると、次女は続いて
次女「だって!お姉ちゃんが勝手に通知表見たもん!!」
長女「え?見てないよ?」
次女「見たらだめって言ったのに見たもん!!」
家族全員 「え…..???」
次女はもう、見たの一点張りです。
はは 「 誰も今、通知表持ってないって」
はは「〇○(長女の名前)、●●(次女の名前)の通知表見たことあるの?」
長女「え?見てないよ?」
はは「●●(次女の名前)、お姉ちゃん見てないって」
次女「見てたもん!!」
はは「前の話?」
次女「…。」
もう、人の話を聞く余裕は次女には無いようです。
次女「だって、先生が人の通知表は見ちゃダメって言ってたもん!!」
「あー。」はは はピン💡ときました。
次女は何か以前に不満を持っていたことを思い出したんだな。
話は逸れますが、次女は決まりごとには厳しいところが見られます。ルール違反は許せません。
ASDの人には良くみられることのようですが、成否の判断がつきやすい規則やルールは、自分の判断基準として取り入れやすいようです。規則やルールはわかりやすい”正解”と言えるので安心して選びやすいのでしょう。
次女にもその特徴は見られ、その”正解”を状況にかかわらず絶対と捉えるので、よくルールを破ることに過敏になります。
そして、それは自分も他人も同等に同じでないといけないという感覚があるようです。
今回は担任の先生が言っていたことですから、次女の中では絶対!というルールがまた一つ確立されてしまったのだと思います。
おそらく何らかのきっかけ、あるいはなんの脈絡もなくかもしれませんが、通知表を見られた記憶を思い出してしまい、過去の姉の行動やその状況がありありと思い出されて、自分がその時、許可なく姉に通知表を見られたことに対して、抱いた不満や、いけないことをしている姉に注意をできなかった不快感などを、突然、今起こったことのように思い出してしまったのだと推測しました。
長女に再び確認すると、そこは「あー、お休み前に学校から帰ってきて通知表の話をしてた時はあったよ?」と言いました。
そういえば、そんなシーンを見た記憶が はは にもありました。二人で通知表を出していた記憶が。そして、姉が自分の成績の話をしながら、次女の通知表と見比べて何か話していた記憶が。
確かこの時も、次女は「人の通知表を見ないで」と言っていた気がします。その時は姉もそれ以上見ようとはせず、その場はそれで終わりました。
フラッシュバック

この時の次女は、おそらくフラッシュバックという状態にあったのではないかと思います。
フラッシュバックとは過去のショックな出来事がなにかのきっかけで突然鮮明に蘇り、まるで再体験しているかのように思い出すことです。
個人的にはPTSDを抱えた人によく聞く話だという印象がありますが、発達障害の人にも起こりやすいようです。
この時の状態としては、本人は思い出しているという認識より過去の体験があたかも今体験しているかのように感じられているそうです。
その理由は特徴的な記憶の仕方と記憶力の良さ、また、不安感を抱えやすいことからくるストレスなどから引き起こされると言われています。
ASDタイプの人の記憶力の良さ 長期記憶と視覚情報処理優位
ASDの人の記憶の仕方には特徴があるという話があります。
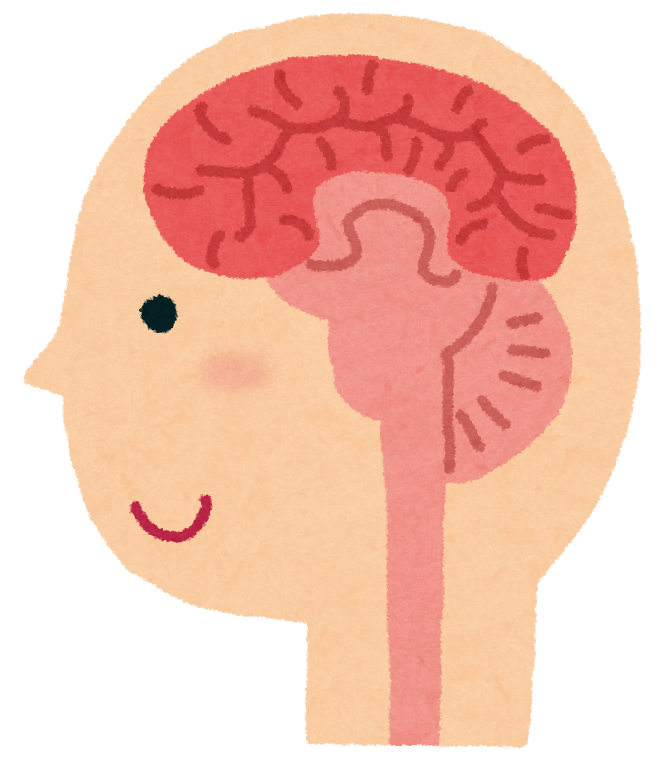
記憶とは
そもそも記憶とは短期記憶と長期記憶から成ります。ASDの人は、中でも長期記憶が優れているのではないかと言われます。
短期記憶とは数秒から数分程度の記憶、例えば買い物に必要なものを思い出し、メモするまでの記憶や一時的に使用した施設のロッカーや駐輪場の位置、番号などを覚えておくというような一時的に保持する記憶で、容量がいっぱいになると先のものから忘れていってしまいます。
一方、長期記憶とは日常的に必要なものの使い方や道順の記憶、短期記憶を繰り返して定着した記憶などの意識しなくても自動的に出てくる記憶、また、強く興味を持つものなどに対する記憶などで、数年や生涯にわたって保持している記憶です。
ここで関係してくるのは長期記憶の方だと思うので、ここでは長期記憶について考えます。
長期記憶が優れている理由
ASDを持つ人が長期記憶が優れている要因としては、不安や感覚過敏などから、不快な記憶、嫌な記憶の印象が強く記憶に残りやすいことや、過去へのこだわりが強いことによって長期記憶を保持する力が強いことによるようです。
私が、ちち や次女を見ていて感じることと、調べたことを総合すると、たとえば、ASDの人で多く言われる他者感情や状況を読み取ることの苦手さがある場合、それに対処する方法として、それまでの生活の中、つまり過去からの経験=情報の収集によって社会生活を成り立たせようと努力しているところがみられるため、過去にあった出来事、体験を、大切なあるいは興味のある情報として強く保持しているのではないかと思います。
こういうと、人は経験を積んで成長していくものなので、それと同じように思われるかもしれませんが、それとは少しニュアンスが違うようで、彼ら、もしくは彼女らの読み取りの苦手さは脳機能からくる苦手さなので、簡単に改善できるものではなく社会生活にはとても困ることになります。そういうどうしても難しいことの対策にいろんな苦労を抱えることになります。
そして、その都度その場の空気や状況判断をすることが苦手であると、何度も嫌な経験を繰り返すことになります。
そうすると、自分の身に危険が伴う困りごとだと感じることが増えて、その嫌な記憶は生きていくための対策に必要な情報として記憶に残りやすくなるのではないかと思います。
そして、それは嫌な記憶、不安な感情を伴う記憶であることが多いので、それがまた恐怖や不安の対象となって、不安ベースの考え方になってしまう。という0-100思考を強めたり、認知の歪みを加速させたりするのではないかと感じます。
発達障害を持つ人、特にASDタイプに寄った人は、自分を守るために保持しておかなければいけない重要な記憶が日常生活にあふれ、長期記憶として残りやすいということではないかと思います。
視覚情報処理の優位
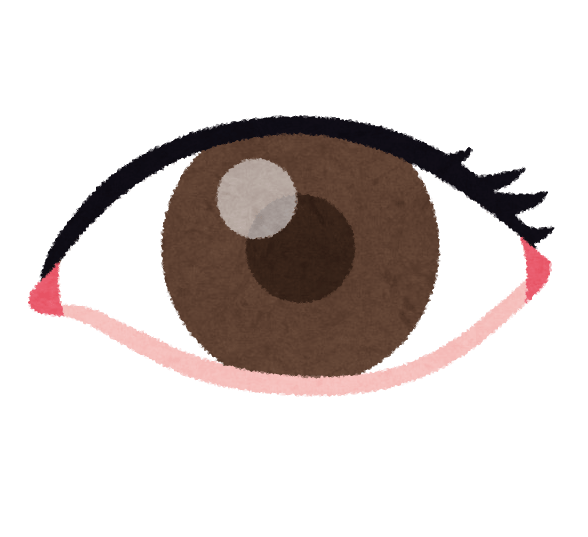
また、発達障害を持つ人は聴覚情報よりも視覚情報の処理が得意なことが多いようです。中には「カメラアイ」と呼ばれる瞬間映像記憶をする人もいるそうです。
次女の場合はカメラアイまでは全く及びませんが、簡単なものなら見た映像を思い返すようなしぐさをすることがあります。
例えば、連絡帳を書き忘れてきたときに、この項目はこう書いていたという記憶をもとに帰ってきてから連絡帳を書いていたことが数回ありました。
その場での処理速度が関係すると書いてこれないことが多々出てくるのですが、平常時の精神状態で冷静に黒板を見るという動作だけを取ると、後々その記憶を引っ張り出してこれるくらい記憶力があるということなのかなと思った出来事です。
また、我が家のちちで言うと 記憶の仕方が映像記憶型のようで、経験した印象に残るシーンを、雰囲気からにおいから情景をそのまま記憶している傾向にあります。日常的にその印象的な状況が思い浮かび、その場の景色の様子や色、匂いを事細かに説明できたりもします。
発達障害を持つ人が必ずしも同じ記憶パターンであるかはまた違う話だとは思いますが、こういう記憶の仕方が得意であるとフラッシュバックを起こす状況はそろいやすいのだろうなと想像しています。
フラッシュバックはストレスと関係している?
ストレスが多いと起きやすいと言われます。が、我が家の様子を見ると、発達障害の人に起こりやすいフラッシュバックは必ずしもそうとは思えませんでした。それとは関係なしに風景などを思い出して懐かしむなどのことも我が家のちち の場合には見られるので、必ずしも良くない条件に起こることではないように思います。
とはいえ、嫌なことの方が記憶してしまいやすいだろうことから、ストレスが強くなると嫌な思い出からのフラッシュバックは増えるかもしれません。
今回のように突然、嫌な記憶をもとに怒りがわいてきてしまうと、周りも翻弄されます。それまでご機嫌で話していたのに突然、今起こったことではないことで相手が怒り出すのですから当然ですよね。
フラッシュバックの対処法 我が家の場合

さて、この対処法としては
- 意識的に違うことを考える
- 落ち着く
- 運動をするなど体を動かして切り替える
などの対処法があると言われますが、次女の場合はまだ小学校2年生なので、もちろん自覚して行動できるという年齢ではありません。
なのでまず、違うことに意識を向ける作戦!
ちょうどお風呂上りでどの下着を着るかで迷っていたので、「どれにする~??」と、次女の「通知表見たら駄目」の合間に話しかけてみました。
が、この時はかなり嫌だと思っていたようで、怒りが収まるどころか増幅している様子で、気をそらすことに失敗しました。
というわけでこの方法は断念。
次は次女理論に入り込む作戦!
次は次女理論に入っていける問いかけをして落ち着かせる!
冷静にその通知表の話に向き合わせてみることにしました。
まずそれを過去に起こっていることだと認識させることにしました。
はは 「それ、前の話だって、お姉ちゃん言ってるよ?」
次女 「見たもん!」

今体感しているんですね。
はは 「今、誰か通知表もってる?」
ちらっと周囲を確認する次女
次女 「ううん」
はは 「じゃあ今は誰も見てないじゃない」
次女「だってお姉ちゃん、見たって言ったもん!!」
通知表を、置いてあるところから取り出して、
はは 「ほら、通知表、ここにあるよ?今、お姉ちゃんが持ってた?」
はは「今は誰も通知表もってなかったよね?ここから出てきたもんね?」
次女「うん…。」
どうやら今起こった出来事ではないことは認識してくれたようでした。
次に先生の「人の通知表をみてはいけません」について、どんな状況においても絶対してはいけないことか、そんなに激怒することなのか、姉との関係性も含めての状況説明をしました。受け入れてくれるかな?
はは 「先生が人の通知表を見てはいけないと言った時は、誰かお友達が勝手に他の子の通知表を見ていたの?」
次女 「うん。」
はは 「そうか、確かに、お友達同士とか他の人の通知表を勝手に見るのはお母さんもよくないと思うよ。けど、絶対にどんなときでも人に見られてはいけないものかな?まず、お父さんやお母さん、は見ることがあるのわかるよね?通知表を確認しないといけないのはお父さんやお母さんのお仕事だしね。」
次女 「うん…。」
はは 「そしたらお姉ちゃんだね。お姉ちゃんは他人じゃないし、長いお休み前で、二人で通知表を出して話をしていたら見ることもあるんじゃないかな?この場合は絶対に見られてはいけないなんてことはないとお母さんは思うよ?でも、見られて嫌だったんどよね?あの時も嫌だって言ってたもんね?でも、嫌だって伝えたらお姉ちゃんは見ないようにしてたよね?」
次女「うん…。」
ちょっとわかりにくい説明かな?納得しないかな?と思いつつ、精一杯話しかける はは です。
すると、話しているうちにだんだん冷静になってきたのか、次女なりに受け入れようと考えてくれている様子。
はは 「どう?通知表の話をしていたら、逆に●●(次女の名前)がお姉ちゃんの通知表を見てたかもしれないんじゃない?」
次女「…。」
多少混乱気味の次女も、そうかもしれないと思ったのか?どうでしょうか?
この場はひとまず落ち着いてくれました。
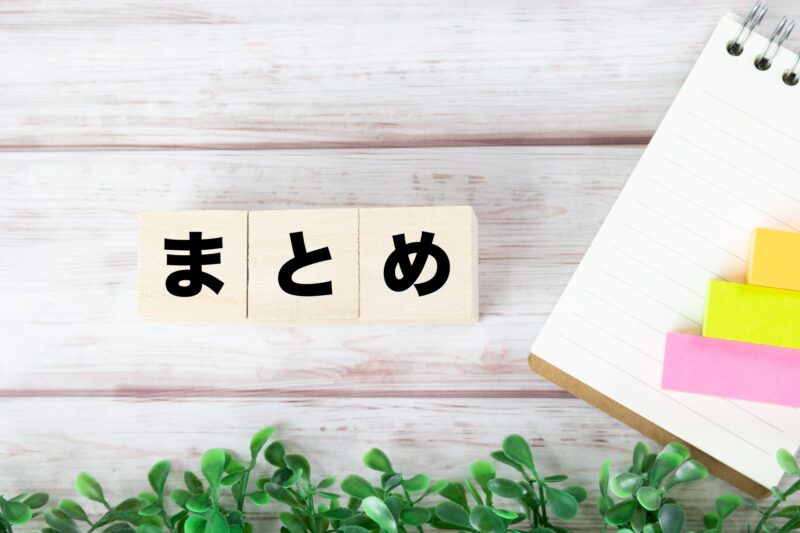
まとめ 正解が一つではないことをいくつものパターンとして経験してほしい
今回は何とか落ち着いてくれた次女でしたが、こういう時に次女の言っていることも間違いではないことが多かったりします。
もちろん、基準としてはそのルール通りなんだけれど、時と場合がある、状況がある、間柄があったり、必ずしもあり得ない!と怒る必要のないことだったりする。そういうことがあるということを伝える方としてはとても難しいなと感じます。
グレーゾーンの考え方を受け入れることは、考えの幅を広げていくことになると思いますが、ASDを持つ人には、恐らく、それらを一つ一つの細かいパターンとして、いくつもの事例を体験してもらうことが大切になるのではないかと、次女やちち を見ていて思います。
そして、ほかの考え方もあるということをどうやって記憶に残してもらえるかもポイントかもしれない。と思ったはは でした。
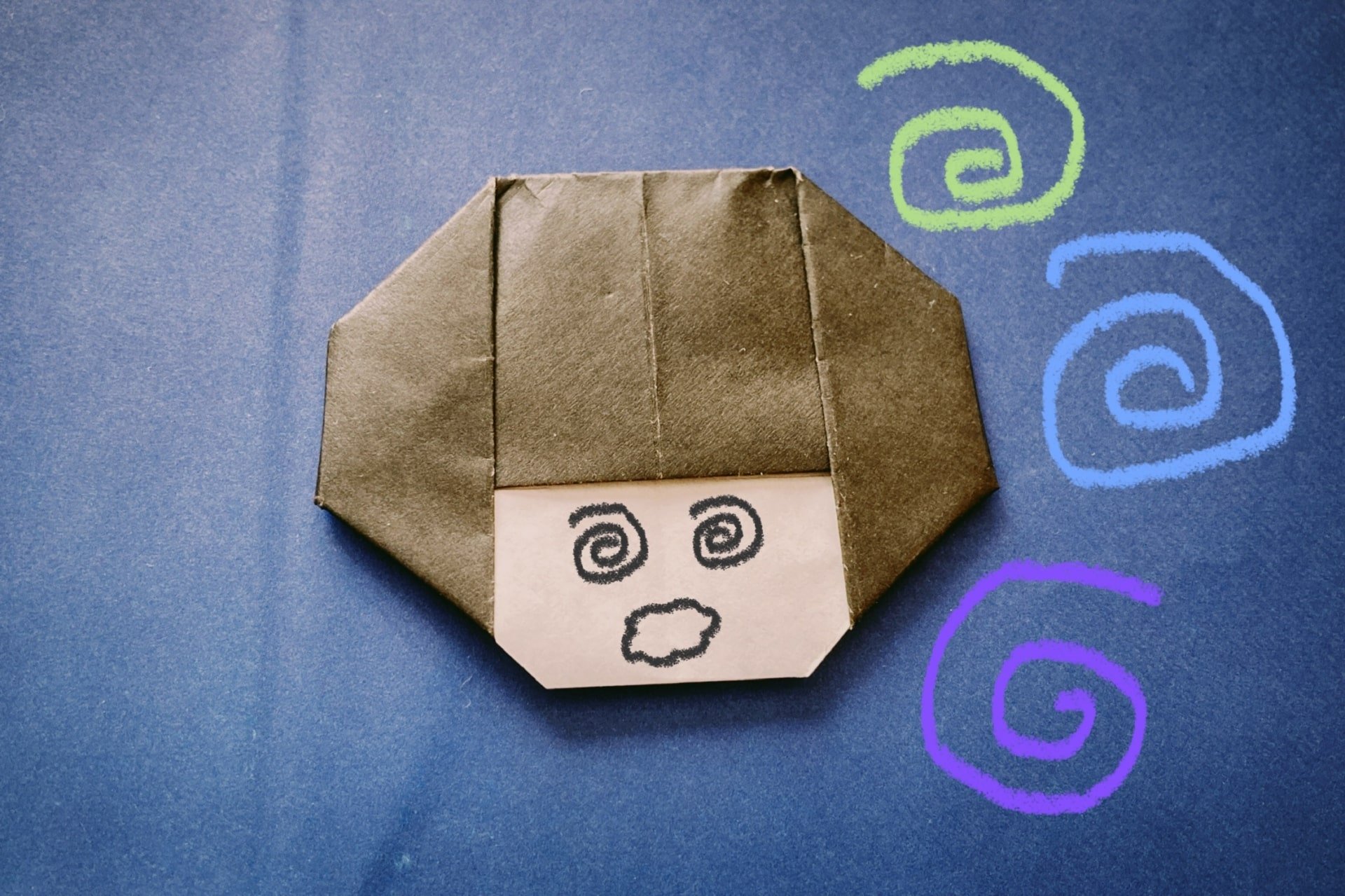



コメント