「日常ー学び」では日ごろの子どもたちの行動や発言から学ぶことや、ちょっとクスっと笑える日常の会話まで、息抜きになるようなお話も書けたらと思います。
次女が帰って来ない理由
ここでは、小学校に入学した次女が一年生になってしばらくすると、授業は終わっているのになかなか帰ってこなくなった話について書きたいと思います。
ゆっくりの感覚 ー 時間感覚のなさ?

次女が小学校に入学して、姉と一緒に毎朝登校することにも慣れてきた頃のことです。授業は終わっている時間なのになかなか帰ってこないことが続くようになりました。
まだ一年生なので、当時小学3年生の姉とは授業の終わる時間帯が違います。
時間が違う日は一人で帰ってきてねと伝えていたので、最初は帰ってきていました。
が、今日は遅いな…?
念のために持たせたGPSを見ると、どうやら校内にいるようです。
まだ校内か…。
…そろそろ門を出たかな?
まだ校内か…。
…どうかな?
まだ校内!?というか、さっきからほとんど動いてないよね!?
度々GPSをチェックすると、どうも校舎を出て正門に続く庭?のようなところをとてつもなくゆっくり移動したり止まったりしている様子…。
???
GPSの不具合で、じつは教室で居残りしているのかしら?なんて思いながら40分ほど経過。
徐々に正門へ近づいてはいるのになぜか学校から出ない。
迎えに行ってみると、先生が庭や校舎の階段の下などで発見してくれて、一緒に帰る。ということが続きました。
???
次女は、「なぜかえって来ないのか?」と聞いても「帰っている!」と言うばかり。
ああ、本人は帰っているつもりなのね。と思いながら、それにしても人ってこんなにスローペースで動けるものなの!?とそのゆっくりさに驚きを隠せない はは。(この時はまだ次女のASDに気づいていませんでした。)
彼女の中の時間はどうなっているのだろう?とか、よっぽど興味のある面白い世界がそこには広がっているのかしら?なんて首をかしげる日々。
その恐ろしくスローペースで移動する次女を担任の先生も目撃していて、「それはもう、すっごい、ゆっくーり歩いていて…。」と笑いながら話してくれたのを覚えています。
当然声をかけてくれたそうですが、そんなことはお構いなしな次女。
そして何度かそれを繰り返したある日、私はふとあることに思い当りました。
一人で帰ることへの不安
我が家は次女も長女も時間の感覚がまるで身につかないので、毎朝、朝の用意って何?状態。朝の集団登校に間に合わせるのに一苦労です。
そこで、私はなぜ集団登校に間に合わないといけないのかを自覚してほしくて、「一人で行っていると危なかったりするから集団登校してるんだよ」とか、「お母さんが心配だから集団登校に間にあうように準備しよう!」と言って呼び掛けていました。
因みに呼びかけをしているときは反応は見られないので、何を考えているのか、効果はあるのか、いやおそらくないだろうといった印象でしたが…。
そして、ふとそのことを思い出した私は、これが原因なのでは!?と思いました。
つまり次女は一人で帰ることが危ないことだということを思い出して、
「できるだけ、いや、絶対に一人で帰りたくない!帰れない!!」
と思っているのではないだろうか?と。
何が何でも!と、姉を待っているために、校内の数メートルを蟻よりも遅い速度で移動して、一応帰っている(?)体で待機しているのではないか?
次女に確認すると、案の定「一人で学校から出ることが怖いのか?」という問いにうなずきました。
それを周囲の大人に言うこともなく、一時間校内にとどまることで解決しようとしていた次女。
言ってくれればいいのに。
兎にも角にも、次女の校内のろのろ滞在事件を解決すべく、放課後の校内活動教室を利用することを決め、姉よりも早く終わる日はそこで待って、姉に迎えにいってもらってから一緒に帰ってくるようにしました。
余談ですが、念のため持たせたGPS、これがなければ謎の解決と見守りができなかったかもしれません。持たせていてよかったと思いました。
主張しない?できない?自分の不安、不満がわからないASD
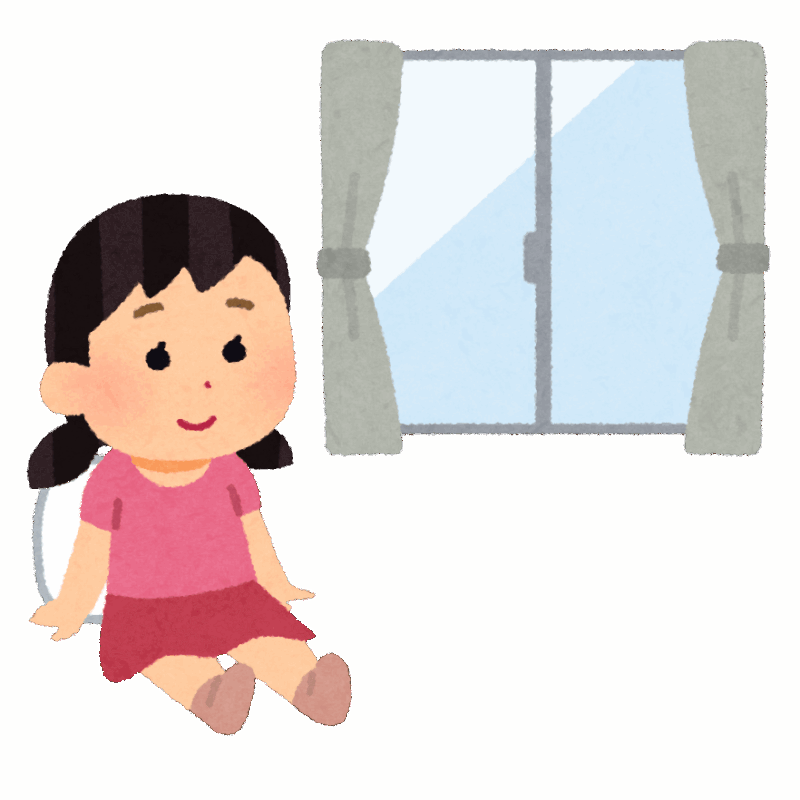
発達障害の特徴には自分の気持ちに気づけない、言語化がなかなかできないというものがあります。
自分の気持ちに鈍感であること、気持ちを言語化、相手に伝わるように話すことが苦手なことが要因だそうです。
我が家の姉妹も以前はまったく自分の感じていること、思った事を言ってくれなかったので、とても困りました。
今でこそ、少しずつ伝えてくれるようになってきましたが、発達障害という考えに出会う前は、子どもたちも気持ちを伝えることができず、こちらも、ただただ考えていることがわからずに一方的に質問するだけになり、答えも返ってこず、寄り添えず、悪循環になっていました。
今回のことも、次女に聞いても「帰っている!」としか反応が返ってこず、「一人で帰ってきてね。」と私が言った事はわかっていて、帰ろうとしているということは伝わってきたので、ただゆっくりいろんなことに気がそれながら帰っているのか、帰るのが嫌なのか、理解に時間がかかってしまいました。
「帰っている!」
次女にしたらそれが事実なのでしょう。そのほかのことは次女自身もはっきり自覚できていなかったのかもしれないなと思いました。
この話は ASD傾向のあるちち からも聞くことができました。
「子どもの頃は特に本当に何も考えていなかったし、特に何事か思っていた記憶はそれほどなかった」そうです。
さらに、私の知り合いにも、子どもの頃も、大人になった今も、「自分のことを考えるってあまりしないな。」という人もいました。
その話を聞いたことで、私はそういう人もいるのだとより実感して、人の考え方は本当に様々であることに改めて気づかされました。
誤解してほしくないのですが、発達障害の人があまり何も考えていないということではありません。
これはあくまで子どもの頃の話が中心の一例としてとらえてもらえると幸いです。そして、まだ発達段階で自分の興味のあるものもあまり生まれていないような時期の話だと思っています。
むしろ、私は発達障害の傾向のある人の方が特定のことに考えが深いようなイメージを持っています。ちち もそうですが、興味のある事柄に関してはとても深く考えることができ、特にASDの方は分析力がとても高いイメージを持っています。
さらに、前述の知人の場合も自分の気持ちを追求できないわけではなく、普段はそれほど重要視していないということだと思っています。そしてそれがその人の人格にとても良く作用しているなと感じています。他人の気持ちなどは考えることはできるし、常識、非常識の範囲もきちんと持っています。
話が少しそれましたが、発達障害を持つ子どもたちとの日ごろのコミュニケーションの中ではこのような主張しないのではなく、特に主張するようなことを自覚していない、不安であること、何に不安であるかがはっきりと認識できずに不安定になってしまっていることがあるようです。
けれど、私は実際、次女がこだわりをもっていることではっきりわかって主張できる感情があったりするので、どちらかというと主張がはっきりしている子だと思っていました。
人間なので当たり前な話なのですが、発達障害における困りごととは、こういったいろいろな要素が絡みあっているもので、今現在に困りごとがある、もしくはこれから困りごとが発生しやすいのではないかと考えることがなかなか難しいなと、個人的には思います。
どちらにせよ、今のところは子どもに今どういう考えが必要かを見つけていけるように、こういった別視点になれる知識は持っていたほうがいいなと思う日々です。
発達障害はグラデーションです。何かは全くできなくて、これは必ずできるという状態ではないそうです。言語化することが苦手なこと。まだ発達途中であること。いろんな状況が混ざり合っているのだろうということ。それらを知って自己理解を当事者自身で整理していくことはとても大変なことなように感じます。けれど、それは社会生活をしていく上ではある程度必要になります。だからこそ、周囲のサポートが大切だと感じています。
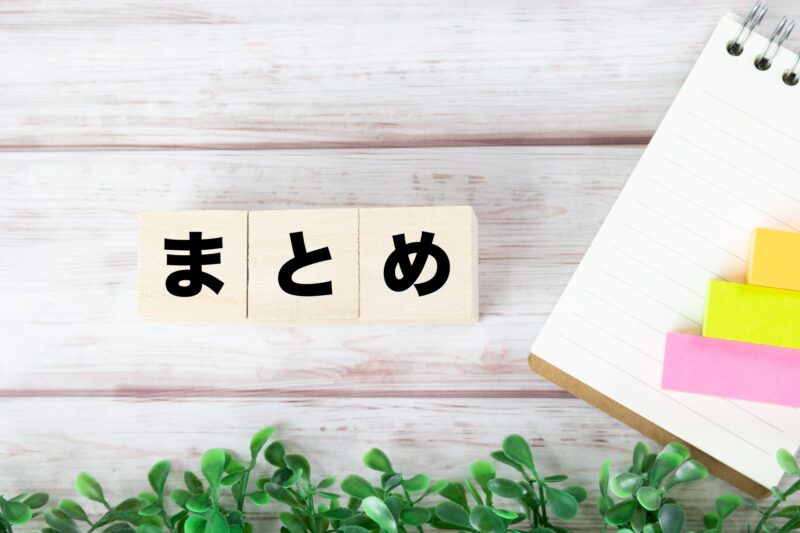
まとめ
我が家では発達障害に気づいてからは、子どもの抱えている気持ちは何なのか?そこを明確にする問いかけや具体的に言語化するとどうなるのかをできるだけ自覚して伝えられるように問いかけたり言語化の例を出してみたりしています。
その気持ちはこうじゃないかな?とか、それをこう言うんだよとか、気持ちの確認、言語化の確認をしたり、「それは悲しかったね」「それは嬉しかったね」などと気持ちの代弁をすることで、次女のことに気づいて半年経つ今は、随分気持ちの表現をしてくれるようになってきました。
また、わからなければわからないと伝えらるようになれることも大切なことだと思うので、「わからない」という返答でもいいと伝えたりしています。
これからも本人が気持ちや状態を伝えれらるように寄り添っていきたいと思っています。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。よかったら、ほかのエピソードにも寄り道していっていただけると嬉しいです。↓




コメント